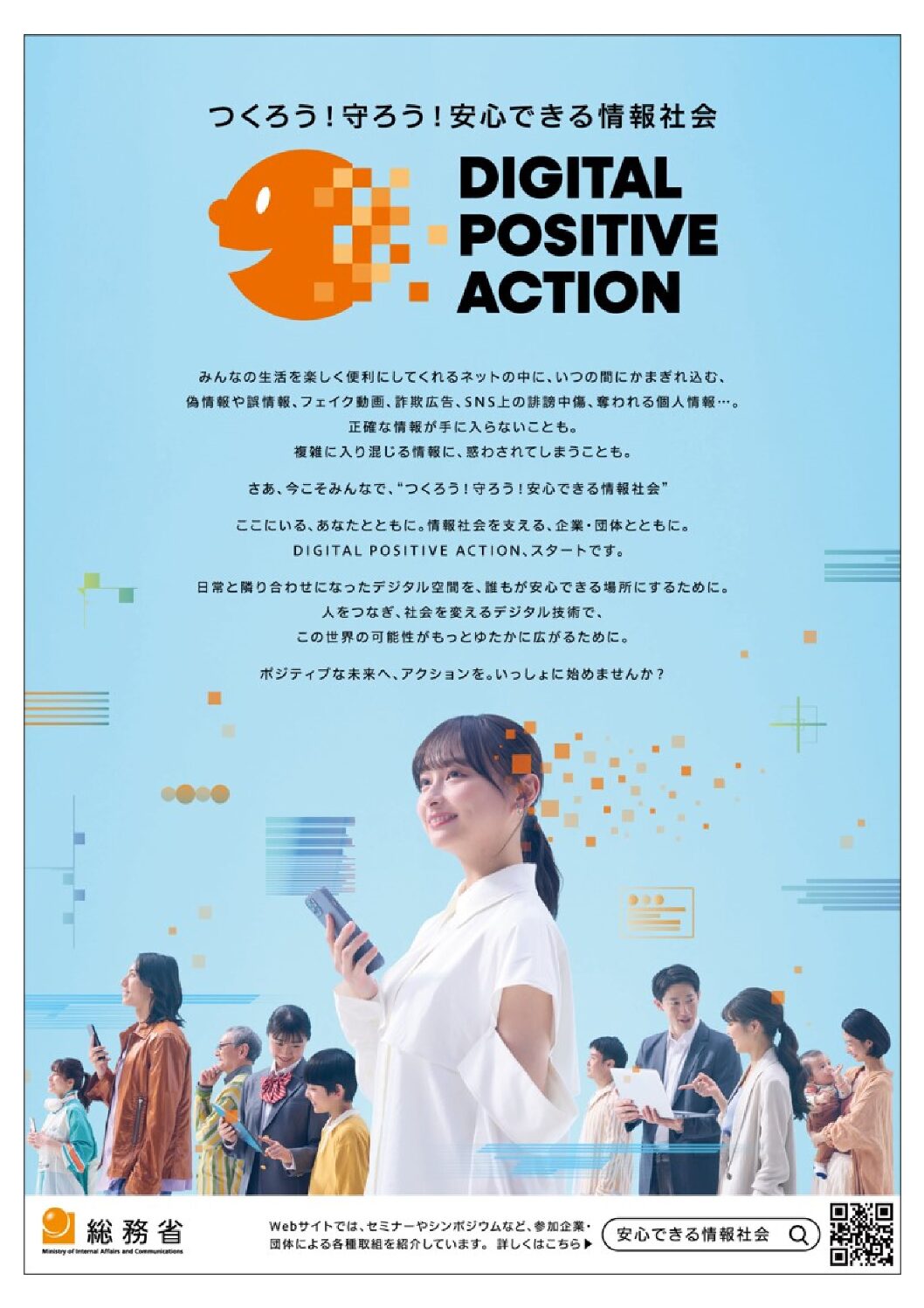
偽・誤情報、4人に1人が情報拡散 総務省ICTリテラシー実態調査
総務省は、利用者のICTリテラシーに関する認識や偽・誤情報の拡散傾向の実態把握を目的に「ICTリテラシー実態調査」の結果を公表した。偽・誤情報に接触した人のうち、4人に1人は何らかの形で情報を拡散したこと、回答者の約9割はICTリテラシーが重要だと考える一方、7割以上が向上に向けた取組をしていないことが判明したという。
この結果を受け、更なる意識啓発を推進するため、テレビ・WebCMの放映を令和7年5月14日(水)から開始する。調査結果とテレビ・WebCMについては、「DIGITAL POSITIVE ACTION」の総合Webサイトでも見ることができる。併せてポスターも公表した=画像=。
調査は、総合的なICTリテラシー向上に向けて、今年1月に開始した「DIGITAL POSITIVE ACTION」に関連して、利用者のICTリテラシーに関する認識や偽・誤情報の拡散傾向等、ICTリテラシーに係る実態を把握し、ICTリテラシー向上の取組を推進するために実施。2025年3月31日~2025年4月2日にかけて、全国47都道府県の15歳以上の男女2820人を対象にインターネットによる定量調査形式で実施した。
調査結果の主なポイントとして、過去に流通した偽・誤情報を見聞きした人に対して、その内容の真偽をどのように考えるか尋ねたところ、「正しい情報だと思う」、「おそらく正しい情報だと思う」と回答した人の割合は47・7%だった。また偽・誤情報に接触した人のうち、25・5%の人が何らかの手段を用いて拡散。若い年代ほどこの傾向が高かったという。
偽・誤情報を拡散した理由は、「情報が驚きの内容だったため」 (27・1%)という回答が最も多かった。次いで、「情報が話題になっていて流行に乗りたかったため」(22・7%)「話の種になると思ったため」(21・0%)「興味深いと思った」(20・9%)、「重要だと感じた」(20・4%)、「他の人にとって有益だと思った」(20・2%)など、情報に価値を感じて拡散したと思われる回答が多かったという。拡散した手段として多いのは、「家族や友人など周囲の人への対面の会話」(58・7%)など身近な人に拡散する回答が多かった。
SNSやネット情報を正しいと判断する基準として最も多いのは「公的機関が発信元・情報源」(41・1%)と最も高く、偽・誤情報に気づいた経緯としてはネット版を含めたテレビ・新聞、ラジオ・雑誌などから偽・誤情報の可能性があると気づいた人が多かった。
「自身のICTリテラシーが高いと思う」という回答は35・2%で、「ICTリテラシーが重要だと思う」、「どちらかといえば重要だと思う」との回答が87・8%と高い割合を示した。一方で、「ICTリテラシー向上に向けた具体的な取組をほとんど行ってない」、「全く行ってない」という回答が75・3%だった。
同省は、インターネットやSNSにおける利用者のICTリテラシー向上を目指し、令和7年1月、官民連携での意識啓発プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」を立ち上げ、趣旨に賛同するプラットフォーム事業者、通信事業者、IT関連企業、関連団体等が参画。プロジェクトでは、「世代に応じた多様な普及啓発」「SNS・デジタルサービスにおけるサービス設計上の工夫」「信頼性の高い情報にかかる表示上の工夫」の方向性で、普及啓発教材の作成やセミナー・シンポジウムの開催、広報活動等、さらなるICTリテラシー向上に向けた取組を推進している。
この記事を書いた記者
- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。






-150x150.png)