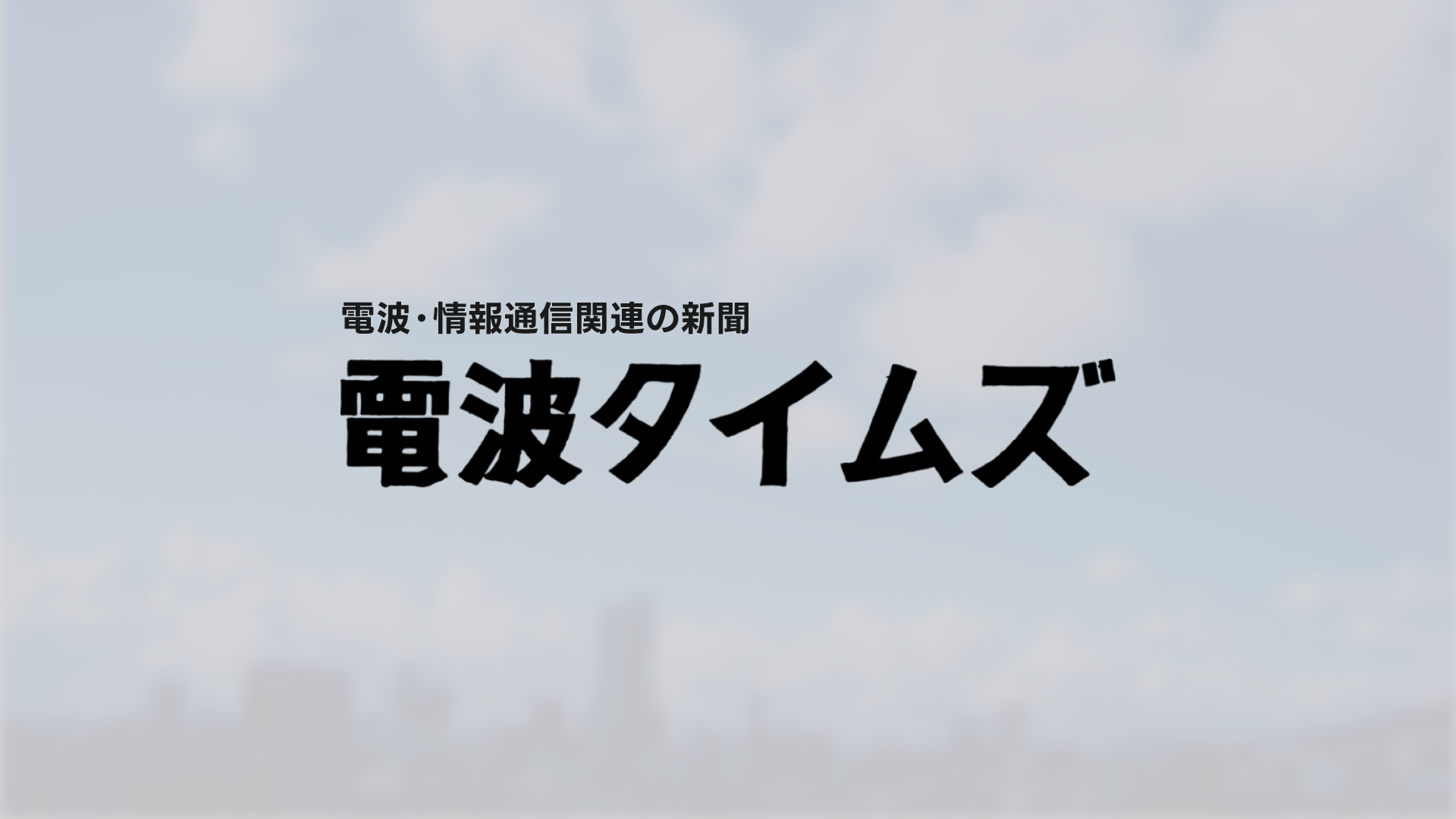
『海の日』式典で海洋立国推進功労者内閣総理大臣表彰
国土交通省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、及び環境省は、7月21日(月・祝)『海の日』午前10時30分から東京都江東区の東京国際クルーズターミナル3階イベントスペースでの『海の日』式典にて、内閣府総合海洋政策推進事務局の協力により「第18回海洋立国推進功労者内閣総理大臣表彰式」を挙行し、海洋立国日本の推進、並びに海洋に特別・顕著な功績のあった5個人・1団体を表彰した。
海洋立国推進功労者表彰(内閣総理大臣賞)は、科学技術、水産、海事、自然環境など海洋に関する幅広い分野における普及啓発、学術・研究、産業振興等において顕著な功績を挙げた個人・団体を表彰し、その功績をたたえ広く紹介することにより、国民の海洋に関する理解・関心を醸成する契機とすることを目的に実施しているもので、今回は「海洋立国日本の推進に関する特別な功績」分野で3個人・1団体、「海洋に関する顕著な功績」分野で2個人がそれぞれ表彰された。受賞者・団体名と功績概要は次のとおりである。
【海洋立国日本の推進に関する特別な功績】
◎小平秀一(61)海洋研究開発機構理事:「大規模海底下探査手法の確立による海溝型地震メカニズムの実態解明に貢献」=深海地下構造調査技術の大規模・大量展開化、超深海化による、海域大規模高分解能地下構造探査の手法を確立し、海溝型地震の発生を規定する地下構造要因を次々と明らかにするなど卓越した研究成果を挙げ、国内外で極めて高く評価されている。また、長年にわたり、その科学的知見や成果の発信、社会実装に精力的に取り組んできた。
◎須賀利雄(63)東北大学大学院理学研究科教授/東北大学・海洋研究開発機構変動海洋エコシステム研究所長:「地球規模の海洋観測網構築による海洋における気候変動研究の推進に貢献」=大洋規模から地球規模までの海洋物理環境の実態と変動の解明に長年にわたって取組み、海洋における気候変動研究の基礎となる多くの業績を挙げた。特に、海洋表面における変動が海洋内部に伝わる課程を独自の手法で定量化する先駆的な研究により、モード水の動態を明らかにし、海の温暖化や酸性化・貧酸素化のメカニズムの枠組み作りに貢献した。
◎多田邦尚(65)香川大学名誉教授/香川大学瀬戸内圏研究センター客員教授:「沿岸海域の環境研究と環境保全及び沿岸海洋学の普及啓発に貢献」=沿岸海域の低次生物生産過程と生元素循環に関する研究を推進。研究助成金を積極的に取得し、名古屋大学・金沢大学、瀬戸内の広島大学・愛媛大学、海上保安大学校、大阪府・兵庫県・岡山県・香川県水産試験場などと共同研究を展開し、東部瀬戸内海の研究・教育拠点として、瀬戸内海の環境研究を牽引した。
◎一般財団法人日本船舶技術研究会(船技協):「海事クラスタープラットフォームによる国際基準・規格の開発・強化」=船技協は発足以来、船舶の基準・規格・研究開発を三位一体となって捉え、海運・造船・舶用工業等の「産」、大学・研究機関・学会等の「学」及び検査機関を含む行政機関等の「官」が一体となった海事クラスターのためのプラットフォームを提供し、海洋立国日本の国際競争力強化のための活動を行ってきた。
【海洋に関する顕著な功績】
◎安田一郎(65)東京海洋大学名誉教授/海洋研究開発機構特任上席研究員:「海洋乱流鉛直混合と海洋・生態系変動の実態解明に貢献」=黒潮大蛇行・海洋中規模渦合体現象の理解、津軽暖流短期変動現象とマサバ漁場形成・予報技術の開発、サンマ漁場形成経年変動・予測、マイワシ漁獲量・資源長期変動と海洋気候変動の関係解明、北太平洋中層水の形成・変質・循環に関する観測・理論的解明、海洋・気候における長期変動と潮汐18・6年周期変動の関係、海洋乱流の簡便な観測による定量化手法の開発と広域観測による乱流物質鉛直輸送と生態系への栄養物質供給過程の理解への貢献等、海洋生態系や機構に関わる未解明だった海洋諸現象の実態と変動の解明を、物理・化学・生物・水産を横断した海洋学際研究によって推進した。
◎辻本勝(54)国立研究開発法人海上・航空技術研究所研究監:「実海域実船性能評価の『ももさし』の開発による海運からのGHG排出削減に貢献」=船舶の推進性能(速力・燃費)推定、実船モニタリングデータからの性能解析法の開発に携わり、その過程で船舶の波・風・潮流、エンジン特性・経年等の影響がある実海域推進性能を高精度に推定する手法を開発した。この手法は国連専門機関の国際海事機関(IMO)で国際海運からGHG排出削減のため開始されたエネルギー効率設計指標(EEDI)規則に反映され、わが国造船業の技術力を正当に、また公平に評価できる仕組み作りに貢献した。
この記事を書いた記者
- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。
最新の投稿
 筆心2026.01.132026年1月13日付(7889号)
筆心2026.01.132026年1月13日付(7889号)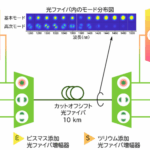 行政2026.01.13NICT、光ファイバでの伝送容量の世界記録を達成
行政2026.01.13NICT、光ファイバでの伝送容量の世界記録を達成 行政2026.01.13総務省令和8年度所管当初予算案概要を公表 前年度比9・7%増
行政2026.01.13総務省令和8年度所管当初予算案概要を公表 前年度比9・7%増 PR記事2026.01.07MCPC安全啓発ロゴとキャッチフレーズを一般募集
PR記事2026.01.07MCPC安全啓発ロゴとキャッチフレーズを一般募集


