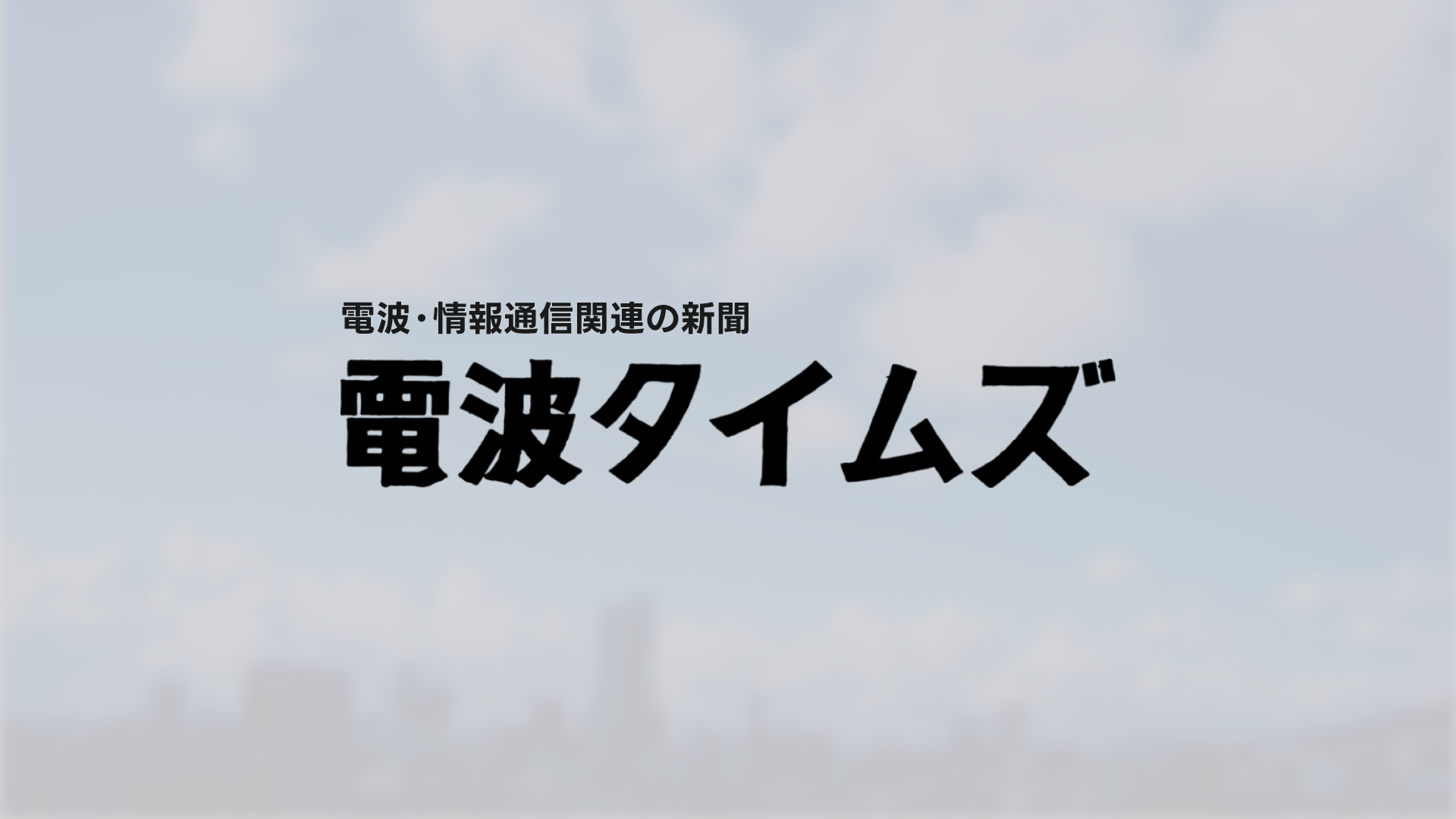
気象庁検討会、地域の気象防災業務で中間取りまとめ
気象庁の「地域における気象防災業務に関する検討会」(座長:矢守克也京都大学防災研究所副所長・教授)は、各地の気象台が実施する地域防災向上を支援する取組みについて、今般、これまでの議論を踏まえた中間取りまとめを公表、本年12月頃の最終取りまとめに向けて検討を進めることとなった。
気象庁では平成30年以降、各地の気象台が地域の防災力の向上を支援する取組みとして、主に防災の最前線に立つ市町村に対して気象庁防災対応支援チーム(JETT)の派遣、気象アドバイザーの活用などを推進。甚大な災害事例を振り返り、都道府県災害対策本部等を通じた市町村支援の重要性や社会経済活動の基盤を担う主体への支援の重要性を確認するとともに、同主体との意見交換を通じて支援のニーズを確認。
外部有識者で構成する「地域における気象防災業務に関する検討会」を開催し、地域における様々な主体との連携のあり方をはじめ、取組みの充実・改善の方向性についての検討を行ってきた。現段階での検討の大きな方向性として、自治体への支援の充実・改善に加えて、ライフラインや交通関係をはじめとする、住民の安全・安心な生活、活動を支える様々な主体に対する支援について、検討が必要とする「中間取りまとめ」を公表した。
従来の市町村を中心とした取組みの充実・改善では、「事前」の取組みについて、市町村の防災対応力向上に向けより一層の支援を行う。地域の防災対応に密着し、市町村における防災気象情報の活用や読み解きに差がある状況も踏まえ、基礎的な内容を扱う丁寧な勉強会・講習会の開催から、実践的なワークショップの実施など、市町村の実情に応じた支援メニューの準備とともに、市町村自らの組織内に防災気象情報を読み解く機能を持つために、気象防災アドバイザーの活用を一層促進する。また、都道府県内での情報共有・コミュニケーションでは、各市町村と緊急時に状況を共有できる関係を事前から構築する一方、市町村が参画する枠組みも活用し、気象台及び関係機関と市町村の間のコミュニケーションを一層推進する。
「災害直前」及び「災害直後」の取組みについて、都道府県との連携強化では、災害関係の情報を集約し、対応の中心となる都道府県の情報連絡室等(災害直前)や災害対策本部(災害直後)と密に連絡。都道府県市町村への支援を円滑に行うため、都道府県の情報連絡室等や災害対策本部等にJETTを迅速に派遣し、状況やニーズ等を収集のうえ関係市町村・主体を支援する。「事後」の取組みについて、災害の経験を次の災害に活かすためにも「振り返り」の取組みは重要で、気象台、自治体の相互理解促進の観点からも、引き続き「振り返り」取組みを積極的に実施するほか、被災地域の復旧作業等に資する気象の見通しや地震活動、火山活動の状況等の解説も積極的に実施する。
社会基盤を担う主体等を対象とした取組みでは、「事前」の取組みについて、現象や防災気象情報に関する職員向け普及啓発、訓練シナリオの作成など防災訓練実施への支援、災害時における国や自治体の動向の事前周知、地域の多様な主体間のコミュニケーションを実施。「災害直前」及び「災害直後」の取組みについて、地方単位などを対象に広域にわたる対応を担う主体への支援、及び避難準備や被災者支援等のための前広な情報提供、緊急時の対応判断に資する国からの情報発信や危機感の共有を図る。地域における特徴的なニーズを踏まえた取組みについては、沖縄県における観光関係の主体への支援等を例に取り上げた。


