
社会課題解決に向けたメタバース導入の手引き公表、総務省
総務省は9月17日、メタバース(没入型技術により実現される空間)の導入を検討する企業や自治体等に役立ててもらうことを目的にまとめた、「社会課題の解決に向けたメタバース導入の手引き」を公表した。
同省では、令和5年10月から「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」(座長:小塚荘一郎・学習院大学法学部教授)を開催し、議論を積み重ねてきた。
同研究会でのこれまでの議論や知見を踏まえ、同省では導入に成功し事業に役立てている企業や自治体等へのヒアリング調査結果をもとに、実例に沿って導入に係るポイント等を盛り込んだ「社会課題の解決に向けたメタバース導入の手引き」を取りまとめた。
手引きは、前段で趣旨と使い方、メタバース導入を成功させるために知っておくべき事項を説明。
メタバース導入を成功させるためのポイントとしては、導入決定に向けた市場調査や先行事例、ユーザ体験を向上させるためのノウハウの把握やビジネスモデルの形成、サービス導入後の効果検証等の方法などを例示している。
後段では、社会課題の解決に資するメタバースの利活用事例として、民間企業や教育機関や自治体など14団体による事例を紹介している。
このうち、学校法人角川ドワンゴ学園の事例では、運営するN高グループ「普通科」でのメタバースを活用したバーチャル学習の取組を紹介。生徒全員にHMD(ヘッドマウントディスプレイ)を貸与し、メタバース上での体験を伴いながらの学習を実践した。2025年4月時点で1万人以上が所属、2025年2月時点で5000本以上のバーチャル授業を受講可能とし、物理や化学の実験や、歴史遺産の訪問、声を出して相手とコミュニケーションを取りながら学ぶことができ、メタバース上での「体験を伴う学習」を通して、集中力や理解力の向上を可能にしたという。従来の動画等による個別でのオンライン学習では、「友達ができる機会を作りにくい」、「運動不足になりがち」などの課題があったが、取組ではメタバース上での生徒の交流イベントや、身体を動かしての体育祭イベントなどを実施することで課題を克服したとし、導入のきっかけや対応の注意点などヒアリング結果も紹介した。
また清水建設(建築事業)の事例では、メタバースによる検査システムを紹介。施工状況の代替として3Dレーザースキャナーで取得した建物空間の高精度な点群データと、確認申請BIM(確認申請に活用した3D設計データ)をメタバース上で結合し、確認申請図書通りに実施されたものかどうかを確認するシステムで、検査者はVRゴーグル(HMD)を装着し、アバターでメタバース内に没入、開発したチェックツール(xRチェッカー)を活用して検査を行う。遠隔での検査が可能になり、現地への移動時間が不要となるため、効率的な働き方が実現できるほか、1日あたりの検査個所数を増やしたり、遠方に住む有資格者の活用によって人材不足の解消が可能となった。また、検査者等の現場での事故リスクや感染リスクを低減し、さらにメタバース上では物理的には不可能・困難な視点変更(空中を移動しての鳥瞰での確認など)が可能となるほか、データ整合の自動チェックによる効率化・的確化など多くのメリットを得ることが可能となった。
順天堂大学では、順天堂医院を細部まで精巧に再現し、入院患者とメタバースで面会できるアプリ「順天堂バーチャルホスピタルメタバース面会アプリ Medical Meetup」を紹介。患者と病院外の人が様々な制約を乗り越え、実際に対面で会わなくてもぬくもりのある面会が実現できるメタバース面会アプリを共同で開発。患者さんと面会者のアバターがリゾート施設等の非日常空間で会話をしたり、外出や乗り物での移動、ハイタッチ等で擬似的に触れ合えるなど、通常の面会の枠を超えた体験を楽しむことができるという。点滴を受けているなどで腕の動作に制限がある患者さん向けに、アバターを操作するコントローラの位置を自身でカスタマイズできる機能など、患者・医療従事者にとっての使いやすさを考慮してデザインし、メタバースを使った医療サービスの構築、臨床現場における有効性の検証に取り組み、患者さんや家族へのよりよい医療の提供へつなげることを目指すとしている。
この記事を書いた記者
- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。
最新の投稿
 筆心2026.01.132026年1月13日付(7889号)
筆心2026.01.132026年1月13日付(7889号)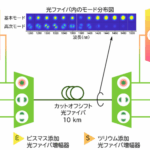 行政2026.01.13NICT、光ファイバでの伝送容量の世界記録を達成
行政2026.01.13NICT、光ファイバでの伝送容量の世界記録を達成 行政2026.01.13総務省令和8年度所管当初予算案概要を公表 前年度比9・7%増
行政2026.01.13総務省令和8年度所管当初予算案概要を公表 前年度比9・7%増 PR記事2026.01.07MCPC安全啓発ロゴとキャッチフレーズを一般募集
PR記事2026.01.07MCPC安全啓発ロゴとキャッチフレーズを一般募集


