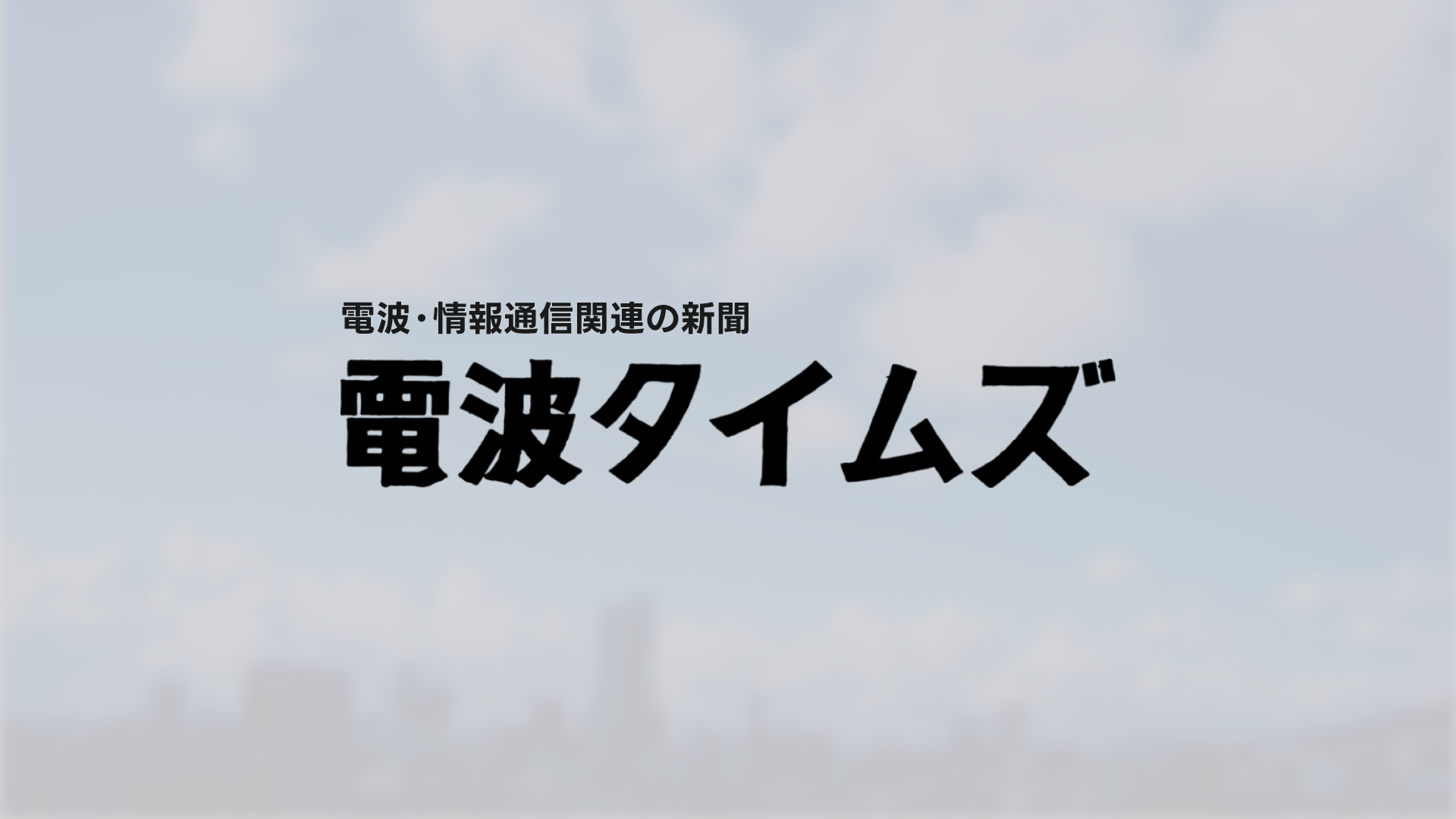
南海トラフ海底地震観測点の追加へ
気象庁は、国立研究開発法人防災科学技術研究所(NIED、茨城県つくば市、寶馨理事長)が高知県沖から日向灘に整備した「南海トラフ海底地震津波観測網(N―net)沖合システム」地震観測データの活用を10月15日(水)から開始し、緊急地震速報の発表の迅速化や制度向上を図ることとなった。四国沖から日向灘にかけて発生する地震について発表する緊急地震速報(警報)が、最大で20秒程度早まることが期待できるという。
防災科学技術研究所は、南海トラフ地震発生時の被害軽減や防災科学技術の発展に貢献することを目指し、南海トラフ地震の想定震源域のうち、それまで観測網が設置されていなかった西側(高知県沖から日向灘)の海底に、地震計と水圧計を備えたN―net(Nankai Trough Seafloor Observation Network for Earthquakes and Tsunamis)を整備した。このN―netは令和6年に整備が完了した「沖合システム」と本年6月に整備が完了した「沿岸システム」から構成する。
気象庁では、海域で発生する地震に対する緊急地震速報の発表の迅速化を図るため、関係機関の協力も得て、沖合に設置された海底地震計の観測データの緊急地震速報への活用を進めている。今般、「N―net沖合システム(18地点)」の地震計についてデータの品質確認等を行い、緊急地震速報へ活用する準備が整ったため、10月15日(水)12時から緊急地震速報への活用を開始することにした。
これにより、前述のように四国沖から日向灘にかけて発生する地震について発表する緊急地震速報(警報)が、最大で20秒程度早まることが期待されている。「N―net沖合システム」の津波観測データについては、令和6年11月21日より津波情報等へ活用されている。気象庁では今後も、緊急地震速報の改善に取組んでいく考えである。


