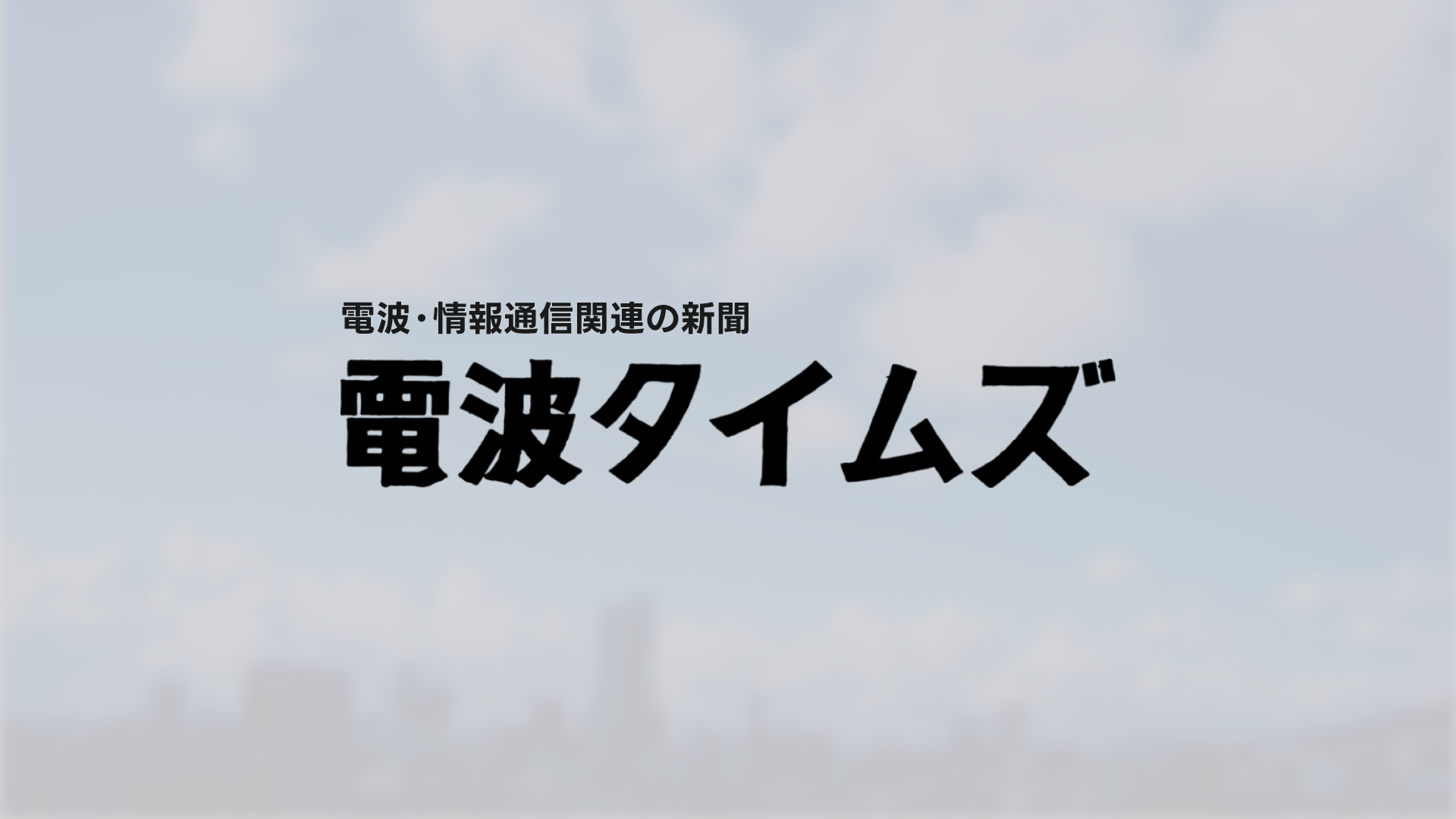
最新の技術革新や多様化するビジネスモデルに柔軟に対応しながらメディア産業の未来を力強く切り拓く
Inter BEEは、日本随一の音・映像・通信のプロフェッショナルが一堂に会し、メディア&エンターテインメント産業の最前線から、コンテンツビジネスに関わる最新のイノベーションを提案する国内最大の「メディア総合イベント」。
60年の歴史と実績を礎に、最新の技術革新や多様化するビジネスモデルに柔軟に対応しながら、メディア産業の未来を力強く切り拓く。
加速度的に進化するメディア&エンターテインメント分野の大きな潮流の中で、コンテンツを「つくる(制作)」「送る(伝送)」「うける(体験)」のすべてのプロセスを網羅するとともに、関わる領域を横断することがいま求められる変化への最適解となりえる。
JEITAは、多角的な情報発信や体験、コミュニケーションを促進する〝プラットフォーム〟として、業界内外に向けて力強く発信し続ける。アフターコロナで加速するオンライン・ハイブリッド需要や生成AIなど新興分野まで、幅広いトピックが一堂に集結し、新たなコラボレーションと次なるイノベーションを創出する場を提供する。
2025年は昨年以上に展示規模が拡大する見込みで、幕張メッセの展示ホール2~8ホール、国際会議場、イベントホールを会場として開催する。メディア&エンターテインメント産業は近年の世界的な市場の復活・拡大にも後押しされ、関連する技術の進展により新製品の市場投入も活発であり、特にAIを活用した新たな技術・製品の拡大とその進化の速度には目を見張るものがある。Inter BEEはメディア&エンーテインメント・テクノロジーの最前線に立つテックイベントとして、61回目となる本年の開催を新たな進化のスタート年として位置付け、産業界の未来を見据えた取り組みをより充実させる。
イベントホールでは、今回10回目を迎えるワールドクラスのSRスピーカー体験イベント「INTER BEE EXPERIENCE X-Speaker」を実施、新たに参加する製品ブランドも加わり、さらなる音響技術の進化を実感する場として展開する。また展示ホールでは、プロユースのヘッドフォン、マイクロフォンを自由に体験できる特別企画「INTER BEE EXPERIENCE X-Headphone/X―Microphone」を今年も実施する。
映像制作分野では、VFXやバーチャルプロダクションといった映像制作技術の最前線を発信し続けてきた「INTER BEE CREATIVE」にて、最先端のクリエイティブトレンドが発信される。また、昨年より映画制作に特化したプロフェッショナルコミュニティとして開始された特別企画「INTER BEE CINEMA」を今年も実施。スクリーン数の増加や作品の体験性が進化・拡大する映画市場を背景に、次世代のクリエイターを刺激する最新動向と技術発信の場として展開する。
放送と通信、メディアとエンターテインメントの垣根がなくなりつつある中、共創と連携の力で新たなメディア時代を切り拓く動きを多角的な視点から発信する特別企画を展開する。旧来の枠組みを超えてメディアの未来を先取りする「INTER BEE IGNITION×DCEXPO」では、放送局とスタートアップの共創、コンテンツとAI、ビジネスの新たな進化への挑戦や先端技術を発信する。
昨年までのINTER BEE BORDERLESSは、今年から「INTER BEE MEDIA Biz」に進化させる。放送メディアにおける加速するビジネス連携の可能性と、進化するメディアに呼応して開花する新たなビジネスの姿、コンテンツの収益化等を多角的な視点から発信する。
放送局のMoIP(Media over IP)とコンテンツ制作のDXを提案する「INTER BEE DX×IP PAVILION」では、「IP」を基盤に注目の「ソフトウェア化」を取り入れ、企業間連携による具体的な提案の場を構築し、制作現場での技術的進化から未来に繋がる次世代コンテンツ制作の効率化を発信する。
国際会議場での「INTER BEE FORUM」と各特別企画会場で行われるコンファレンスは、同時開催の「第62回民放技術報告会(主催・企画:一般社団法人日本民間放送連盟)」のセッションや出展者セミナーなどと合わせ、100以上のセッションを予定している。
今年の基調講演は、11月19日10:00~11:30「Inter BEE 2025 Opening & Keynote」では主催者あいさつを漆間啓氏(一般社団法人日本電子情報技術産業協会)、「放送政策の最新動向(仮)」を豊嶋基暢氏(総務省 情報流通行政局長)、「デジタル技術と日本のコンテンツ産業(仮)」を梶 直弘氏(経済産業省 商務・サービスグループ文化創造産業課長)、「情報空間の参照点を目指して―NHK ONEと公共放送の新たな役割」を山﨑 英一氏(日本放送協会 メディア総局 副総局長)。
同13:00〜14:00には、「ドジャースはなぜ投資するのか?球団もテレビ局も“投資家”になる時代」と題して、Jay Adya氏(Elysian Park Ventures Managing Partner)と増澤 晃氏(テレビ朝日 経営戦略局 投資戦略部オープンイノベーション担当部長)が語る。モデレーターは宮田拓弥氏(スクラムベンチャーズ 創業者兼ジェネラル・パートナー)。
同14:30〜15:30には「テレビドラマに革命を起こすAI映像」が行われる。同講演では、読売テレビが制作した、全編に生成AIを使用することで動画生成AIの「可能性と限界」に挑戦したショートドラマ『サヨナラ港区』を題材にテレビドラマに革命を起こすAI映像について、AIクリエイターの宮城明弘 氏とプロデューサーの汐口武史氏に講演する。モデレーターは、ジャーナリストのまつもとあつし氏が務める。
20日10:30~12:30には「IPTVフォーラム企画:放送とネット配信の両輪で創るテレビサービスの未来~アドレッサブルTVからフェイク対策まで~」と題して、特別講演として「放送・配信関連政策の最新動向」を横澤田悠氏(総務省 情報流通行政局 放送業務課 配信サービス事業室長)が講演する他、パネルディスカッション:放送とネット配信の両輪で創るテレビサービスの未来~アドレッサブルTVからフェイク対策まで~を行う。パネリストは飯塚留美氏(一般財団法人 マルチメディア振興センター 調査研究部・研究主幹)、伊藤正史氏(フジテレビジョン メディア技術開発部 兼メディア企画室)、西村敏氏(一般社団法人 IPTVフォーラム ハイブリッドキャスト推進連絡会 技術部門リーダー)、出葉義治氏(一般社団法人 IPTVフォーラム CTA WAVEリエゾンパーソン)、モデレーターは土橋由実氏(三菱総合研究所 モビリティ・通信政策本部 ICTインフラ戦略グループ 主任研究員)。
同13:00〜14:30には、「イマーシブ・サウンドの現状と今後の動向Part Ⅱ≪ パッケージ・放送/配信・教育現場 ≫」を開催。パネリストは高田 英男氏(ミキサーズラボ サウンド・プロデューサー/レコーディング・エンジニア)、入江健介氏(日本放送協会 メディア技術局 コンテンツテクノロジーセンター コンテンツサービスグループ(音声))、戸田佳宏氏(WOWOW 技術センター コンテンツ技術ユニット エンジニア)、長江和哉氏(名古屋芸術大学 サウンドメディア・コンポジションコース 教授)、モデレーターは阿部健彦氏(テレビ朝日 技術局設備センター)。
21日(金) 10:30~12:00には「クラウドが駆動するメディアDX:放送局の基盤構築から、生成AIが拓く未来まで」を実施する。
まず「現場が選ぶクラウド:フジ・ネクステラ・ラボ×Oracle Cloud Infrastructure の答え」を福元陸郎氏(フジ・ネクステラ・ラボ 放送ソリューション部 部長)、廣瀬一海氏(日本オラクル クラウド事業統括エグゼクティブ・アーキテクト)が語る。
次に「AIが変えるメディアの未来:創造力とテクノロジーの新境地」をDillen Alahendra 氏(マイクロソフト Chief Director of Telco, Media & Gaming Worldwide,)を講演する。
最後に「融合するエンターテインメント:生成AIとクラウドが実現する新たな視聴体験」を中澤優一郎氏(AbemaTV Development Headquarters Content & Data Division/Principal Content Engineer)、山口賢人氏(アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 インダストリー事業開発マネージャー)が語る。
同12:30〜14:00には「『最初の一歩』の最適解 ― グランドデザイン構想と現場の実践から学ぶ、放送局IP化のリアル」を開催。パネリストは高畑陸氏(WOWOW 技術センター コンテンツ技術 ユニット)、齊藤徹氏(WOWOW 技術センター 設備プロダクトユニットエンジニア)、皆内圭介氏(南日本放送 報道制作局制作技術部 副部長)、齊藤力弥氏(池上通信機 放送システム技師長)、モデレーターは榎戸真哉氏(ネットワンシステムズ 東日本第3事業本部 エンタープライズ事業戦略部 プリセールスチーム エキスパー)。
◇
また、昨年より開始した「INTER BEE AWARD」を本年も継続して実施。最新の技術動向を踏まえ、会場に展示され応募された製品・サービス等の中から、より優れていると評価されるものを選考し表彰、広く発信する。INTER BEE AWARDの最終審査は11月19日(水)に展示会場で行い、同日夕方に発表・表彰する予定。
この記事を書いた記者
- 放送技術を中心に、ICTなども担当。以前は半導体系記者。なんちゃってキャンプが趣味で、競馬はたしなみ程度。
最新の投稿
 プレスリリース2026.01.06サンディスク、SANDISK Optimus SSD製品ブランドを発表
プレスリリース2026.01.06サンディスク、SANDISK Optimus SSD製品ブランドを発表 プレスリリース2026.01.06CES 2026でグローバル市場に新たな価値を提示したWi-Fi 8ルーターや革新的な240Hz ARグラスなど次世代ゲーミング革新製品を一挙発表
プレスリリース2026.01.06CES 2026でグローバル市場に新たな価値を提示したWi-Fi 8ルーターや革新的な240Hz ARグラスなど次世代ゲーミング革新製品を一挙発表 実録・戦後放送史2026.01.06「カラーテレビの登場㉑」
実録・戦後放送史2026.01.06「カラーテレビの登場㉑」 放送2026.01.06NHK稲葉会長に聞く~新しい時代の「メディア」として前進
放送2026.01.06NHK稲葉会長に聞く~新しい時代の「メディア」として前進


