放送100年 特別企画「放送ルネサンス」第29回
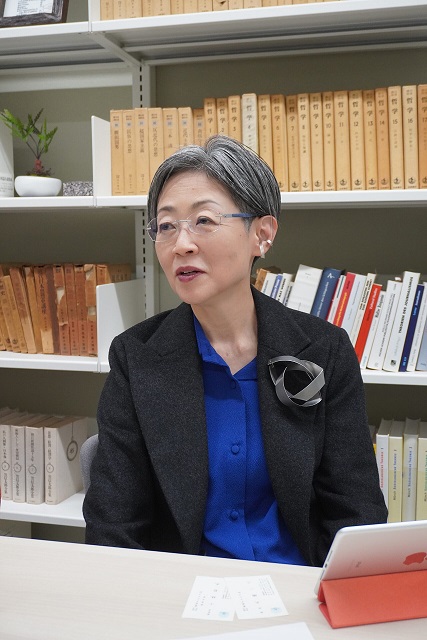
東京大学理事・副学長
林 香里 さん
林 香里(はやし・かおり)氏。1963年、愛知県名古屋市生まれ。1987年、南山大学外国語学部英米科卒業。ロイター通信勤務を経て1995年、東京大学大学院社会学研究科修士課程修了。同大大学院人文社会系研究科博士課程中退。社会情報学博士。現在、東京大学大学院情報学環教授。同大理事・副学長。2012年度から2015年度まで、BPO 放送倫理・番組向上機構 放送と人権等権利に関する委員会(放送人権委員会)委員を務めた。
林 香里さん インタビュー
Contents
- 1 ―ご自身と放送との関わりについて
- 2 ―メディアの研究者となったのは、そうした影響もあったのか
- 3 ―放送開始から100年が経つが、放送の果たしてきた役割をどう考えるか
- 4 ―海外と比較した日本の放送の特徴は
- 5 ―社会的な役割という意味での放送は劣化しているか
- 6 ―ジャーナリズムとしての放送の役割も変容しているか
- 7 ―兵庫県知事選では従来のメディアとSNSとの比較も話題になった
- 8 ―放送終焉の声がある中、放送が生き残るには
- 9 ―形態としての放送は必要がなくなるのか、それとも残るべきなのか
- 10 ―今の放送はどう見直していくべきか
- 11 ―今後放送とネットはどう関わっていくべきか
- 12 ―これからの放送に対して提言を
―ご自身と放送との関わりについて
私にとって放送は、出会うというより生まれたときから既にある存在。毎日テレビがついていて、朝のニュースを見て、帰って来たらまたテレビが茶の間でついていて、という家で、中学ぐらいまでは本当によくテレビを見ていた。しかし、高校生ぐらいになってテレビに飽きてしまい、そこから海外に留学したりして日本のテレビから離れる時期がずいぶんあった。
ただ海外で子育てをしていていたとき、日本のテレビ番組が見られるケーブルチャンネルで「おかあさんといっしょ」などの日本語番組を見たりしていた。その頃はまだ、今のようにどこに行ってもインターネットがある時代ではなく、そういう意味ではテレビが日本語情報源として重要な時代だった。
―メディアの研究者となったのは、そうした影響もあったのか
私は媒体としてのテレビより、どちらかというと、ジャーナリズムとかニュースの方に興味があったので、それでジャーナリストとか記者になり、大学でもジャーナリズム研究を専門にしている。テレビは専門というわけではないが、日本のテレビは基本的に娯楽メディアのイメージが強い。研究者になって、そのことに確信を抱くようになった。
―放送開始から100年が経つが、放送の果たしてきた役割をどう考えるか
日本のテレビは影響力の強いメディア。特に娯楽の分野でテレビは中心的役割を果たしてきた。高度成長時代には、日本の成長と同期しながら、国民にニュースだけでなく、広い意味での情報、娯楽、さらにライフスタイル全般を提供してきた。そういうメディアだと思う。
放送、とくにテレビには、国民を統合する機能が負託されてきた。良い意味でも悪い意味でも100年の間、国民に向けて「日本」という国を表現してきたメディアだと思う。私達が何をしてきたか、どういう社会に住んでいるかをテレビが拾って国民に見せ、社会を引っ張ってきた。標準語もそうだが、国民にとってどういう生き方が良い生き方なのかという、ある意味での規範もテレビが示し、普及させてきたように思う。
―海外と比較した日本の放送の特徴は
戦後の日本の放送事業の特徴は、商業放送(民放)と公共放送の二本柱だったことだ。ある意味で、公共放送と商業放送の2者の緊張感関係によるダイナミズムで動いてきたところがある。NHKは戦前の国営放送を引き継いだ形だが、商業放送は、当初はNHKの官僚的で国策的な側面に対抗するリベラルな存在だった。民衆に寄り添う、かなり実験的な番組もあって、それが「民間放送」と呼ばれる所以でもあった。しかし、次第に商業主義が台頭し、視聴率重視へと大きくシフトし、現在に至っている。
他方で、多メディア化していけばいくほど、放送事業そのものの基盤が危うくなり、全体的な放送事業の地盤沈下が進んだが、欧米のように放送局が買収されたり、合従連衡を繰り返したりという組織的変化が少ない。新規参入も難しく、放送局は非常に保護されている。私はいろいろな国に行く機会があるが、海外のテレビを見ると、テレビチャンネルが1970年代と現代の2024年とが変わらず、ほぼ同じラインアップなのは日本くらいしかない。
―社会的な役割という意味での放送は劣化しているか
劣化していると思う。まずは視聴の短時間化が進んでいる。そして、テレビは高齢者のメディアになっている。高齢者のメディアだから即劣化しているというのは暴論かもしれないが、では若い人たちが高齢になればテレビに戻るのかといえばそうではないだろう。
こうした社会的なステイタスの地盤沈下に伴い、受信料収入で運営されていて、市場原理からは隔離されているはずのNHKも商業主義に引っ張られてしまっている。また、報道部門では、商業放送、NHKともに、政府との距離の取り方が気になる。とくに安倍政権時代には陰に陽に圧力がかかり、現場が萎縮してしまって、言論・表現の面からも劣化している。
―ジャーナリズムとしての放送の役割も変容しているか
統計を見ると、日本人の情報源としてはまだまだテレビは強く、特に災害情報等ではテレビは圧倒的に市民からの信頼も厚い。実際に災害が起こった時の臨時放送の体制は素晴らしいものがあると思う。
しかし、政治や社会に関する報道については、しっかりと現代社会の事象にアンテナが立っているか、政府から独立した報道ができているかというと心もとない。「モリカケ」や「ジャニーズ」など、新聞や週刊誌がスクープを出したということは聞いたことがあるが、テレビがスクープしたという話はこのところあまり聞かない。
―兵庫県知事選では従来のメディアとSNSとの比較も話題になった
テレビの選挙報道ほどつまらないものはない。公職選挙法と放送法によってがんじがらめになっていて、必要な情報も得られない。政見放送も時代遅れ。そういう視聴者の気持ちが長くあるにもかかわらず、テレビは積極的に動いてくれないし、ジャーナリズムの責任感も伝わってこない。
そもそも、総務省が放送の許認可主体というところも、私達研究者はずっとおかしいと指摘してきた。第三者機関など、政府以外の組織を作って間接的に監督するべきで、総務省が直で免許交付をするのは、自由主義国では日本だけ。民主党政権のときに「日本版FCC」構想が出たが立ち消えとなり、今日まで総務省が管轄している。近年では衛星放送事業者が総務省へ高額接待をしていたというニュースもあり、希望をもてない。

―放送終焉の声がある中、放送が生き残るには
まずは「放送」と一口にいっても、さまざまな切り口がある。コンテンツ面で言えば、映像の制作のノウハウの蓄積はある。また、過去のコンテンツのアーカイブも存在する。したがって、映像コンテンツ事業は残る。また、一斉送信としての放送という媒体インフラも必要だと思う。
新たな映像コンテンツ事業、放送事業の構想を描ける人材は、まだ日本にいるはずだ。ただ、現在の放送事業者の中にそのキャパシティがどれだけ残っているか疑問だ。
とくに、ローカル局で自社コンテンツを10%ぐらいしか作っておらず、それにもかかわらずフルセットで装置を持って「テレビ局」と名乗っているような事業所はもういらないのではないか。昔ながらの、ローカル局がキー局の中継局みたいになっていて、おまけに系列局や新聞社から来た人が社長になるというような仕組みの会社は生き残れないと思う。
―形態としての放送は必要がなくなるのか、それとも残るべきなのか
海外の場合はコンテンツとコンジット(導管)が解体されて、映像と装置が切り離されてきた。今の日本では、まだそれが混然一体となっていて機動力がない。世界の流れではコンテンツとコンジットの分離後、放送事業は再編され、コンテンツ産業としての発展がカギとなっている。日本では戦後に生まれた放送事業者がそのまま生き残っており、経営スタイルにも大きな変化がない。周回遅れの状況だ。
テレビを見たいと思う人もまだいるし、映像には訴求力もある。しかし、次の100年で日本の放送事業のプレーヤーがどうなるか、産業構造がどう変化するかは、ちょっとわからない。私自身は利潤追求に貪欲なテック産業によって支配され、さまざまに分断される社会状況を見るにつけ、とくに公共放送という制度をとても大切だと思っている。残ってほしいとも思っている。
けれども、いまのNHKがどこまで現代の社会の真のニーズに応えられる組織になれるか、社会の重要な情報インフラになっていくことができるかと考えると、やはり抜本的に組織のあり方を考え直す時期にあるのかと思う。
―今の放送はどう見直していくべきか
日本では、日本語がバリアとなって、放送の異なるあり方を知る機会が少ない。多言語番組や市民参加型の番組、アーカイブ・コンテンツなど、いろいろな放送の可能性があるのに、そのポテンシャルを出し尽くしてないのではないか。そこをもっと開拓して放送で何ができるかをもっと考え挑戦する必要がある。そうした放送局があれば、生き残れると思う。
なにより、番組を作る元気がないと放送事業者は終わってしまうが、現在ではテレビ局は視聴率がトッププライオリティ。さらに番組制作会社に制作を外注する割合が高くなっており、クリエイティブな場ではない。
他方で、ネットではアテンションエコノミーが加速化し、意外性や新奇性が真実性よりも価値ある状況が作り出されている。フェイクニュースや、根も葉もない誹謗中傷が拡散されたり、あるいはフィルターバブルの中で生きる人々が互いの共通意識をもちにくい社会になってしまったり。情報化時代、コミュニケーションが活発化して人々がつながるというかつての希望は潰えて、社会は非常に不安定な状態になっている。
こういう状況の中、一斉送信ができるインフラストラクチャーとしての放送の可能性を真剣に検討しなくてはならない。
―今後放送とネットはどう関わっていくべきか
以前に私が行った内容分析調査では、日本のネット情報はエンターテイメントに偏っていて、報道機能が弱く、人々が民主的な社会の運営に際して知るべきニュースを十分に提供してない結果が出た。また、ネットメディアはグローバルだと思われがちだが、ネットニュースはどちらかというと国内ものが多く、海外ニュースが弱い。
そういう意味ではネットが放送に置き換わっていくというよりは、放送をはじめ、伝統的なメディアがネット空間に適切にニュースを供給していけるかどうかが問われている。
―これからの放送に対して提言を
まず組織のイノベーションをしてほしい。2025年に発覚した有名人気タレントと女性のトラブルに対するフジテレビの対応からも明らかなように、組織の透明性の欠如、危機管理の不備、そして世論とかけ離れた対応は、大手メディア企業全体が当事者意識を持って考えるべき問題である。組織が古く、人権意識も弱く、社会情勢についての感度も鈍い。このままでは信頼回復も難しいだろう。
まずはリーダーシップの刷新だ。リーダーがちゃんとしていないと組織は変わらない。年功序列、終身雇用に慣れ切ったシニアの男性たちでは、社や業界の何をどう改革に導けばよいのかの明確なビジョンも持てず、変革の敢行も難しいのではないか。総務省による免許制が生む官民癒着も心配だ。
日本ではプロフェッショナルなジャーナリスト同士がつながる職業団体がないので、会社を超えた話し合いの場もない。何か変えようと思っても、会社の利益が優先してうまくいかない。まずは会社の利害を超え、もう少し高次元のレベルでのビジョンを持って、日本の放送事業を何とかしようと考え、話し合えるプラットフォームが必要だと思う。
ネットと放送の境界線がわからなくなってしまった時代、これまでの典型的なテレビ「業界人」とは異なる属性やスキルをもった人たちが集い、創造力と能力を発揮できるような業種に生まれ変わらなければならない。
この記事を書いた記者
- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。
最新の投稿
 行政2025.07.11MWCバルセロナ2026日本パビリオンの参加募集
行政2025.07.11MWCバルセロナ2026日本パビリオンの参加募集 情報通信2025.07.11フェリーWi―Fiを本格展開開始、KDDI等Starlinkを活用
情報通信2025.07.11フェリーWi―Fiを本格展開開始、KDDI等Starlinkを活用 行政2025.07.11ワンコイン浸水センサの取組み拡充、国交省が232自治体で実証実施
行政2025.07.11ワンコイン浸水センサの取組み拡充、国交省が232自治体で実証実施 行政2025.07.11総務省人事異動(2025年6月28日~7月7日付)
行政2025.07.11総務省人事異動(2025年6月28日~7月7日付)
本企画をご覧いただいた皆様からの
感想をお待ちしております!
下記メールアドレスまでお送りください。
インタビュー予定者
飯田豊、奥村倫弘、亀渕昭信、川端和治、小松純也、重延浩、宍戸常寿、鈴木おさむ、鈴木謙介、鈴木茂昭、鈴木秀美、
西土彰一郎、野崎圭一、旗本浩二、濱田純一、日笠昭彦、堀木卓也、村井純、吉田眞人ほか多数予定しております。
(敬称略:あいうえお順)


