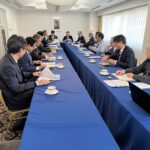【放送ルネサンス】第40回:砂川 浩慶さん(立教大学 社会学部 学部長 メディア社会学科教授)

立教大学 社会学部 学部長 メディア社会学科教授
砂川 浩慶 さん
砂川浩慶(すなかわ・ひろよし)氏。1963年沖縄・宮古島生まれ。86年早稲田大卒、同年日本民間放送連盟(民放連)に入り、2006年まで放送制度、著作権、広報、機関紙記者、地上デジタル放送などを担当。2006年立教大学社会学部メディア社会学科開設とともに移り、准教授、教授。2023年から社会学部長。研究テーマは放送制度、ジャーナリズム、コンテンツ流通、メディア規制等。著書に「安倍官邸とテレビ」(集英社新書)など。
砂川 浩慶さん インタビュー
Contents
- 1 ―ご自身と放送との関わりについて
- 2 ―放送開始100年となるが、放送の果たした役割をどう評価するか
- 3 ―そうした放送の役割は変わってきたと思うが、現状をどう見ているか
- 4 -放送はかつての影響力は失いつつあると・・
- 5 ―しかし、若い人のテレビ離れは放送にとって深刻な問題だと思うが
- 6 ―この先、放送はどう生き残るのか、また生き残ることは出来ると思うか
- 7 ―この先の放送局の経営の行方をどう見ているか
- 8 ―ローカル局はどうなっていくとみているか
- 9 ―日本の放送局の体制はどういう形になっていくと思うか
- 10 ―放送波を使った仕組みとしての放送の今後はどう見るか
- 11 ―放送はインターネットとどう関わっていくべきか
- 12 ―ネットに出ていくことで放送の質は低下しないか
- 13 ―一連のフジテレビ問題をどう見ているか
- 14 ―ある種共通の課題があるということか
- 15 -最後にNHKの今後について
―ご自身と放送との関わりについて
学生時代にNHKでアルバイトをしていて、放送に興味を持つようになり、民放連に入った。その後、大学に移って、民放連と大学でそれぞれ20年、あわせると約40年放送に携わってきた。人生の3分の2は放送に関わっていて、もはや放送と一心同体の感じがする。
大学に移ってからは、学生に教える立場として、放送を客観的に見るようになった。ゼミの学生が多く放送業界に就職しており、放送局は、ちゃんとしていてくれなくてはダメだというのが今の放送への思いでもある。
―放送開始100年となるが、放送の果たした役割をどう評価するか
放送の果たしてきた役割は、特に日本では大きく、日本の文化水準を押し上げてきた。標準語を全国にいきわたらせたのもNHKなど放送であり、放送を通じて、教養だけでなく娯楽、スポーツなどを広めてきた役割は大きい。新聞もあるが、全ての国民が同じものを見聞きできるようにしたのは、当時でいえばNHKだけであり、その意味で、放送は、これまでは十分に役割を果たしてきたと思う。
―そうした放送の役割は変わってきたと思うが、現状をどう見ているか
現在、50歳代までの人は、少なくともテレビで育ってきたテレビ世代であり、この先、30年は、そうした人たちに支えられ、テレビは維持されると思う。しかし、40代以下は余りテレビを見ない世代であり、大学の授業で学生のメディア接触調査をしているが、今回、初めて紙の新聞への接触がゼロになった。80%は自宅から通学しているが、要するに自宅で新聞をとっていないということだ。放送も今の40代以下の世代になってくると、新聞の接触と近い状況になってくるだろう。そうした状況を考えれば、日本の文化水準の向上に寄与してきた、これまでの放送の役割は、だいぶ変わらざるを得ないだろう。
-放送はかつての影響力は失いつつあると・・
放送波という独占的な伝送路が、ネットの登場で多様化していることを考えれば、残念ながらテレビの影響力は相対的に低下せざるを得ない。スポーツ中継でも、若い人たちはスマホで見るようになっているが、彼らに聞くと、テレビで見たいが、ネット中継しかないので、やむを得ないという。スポーツ中継においても、放送局が一緒に中継権を購入するコンソーシアムが成立せず、中継がネットに代わってきていて、放送の影響力は低下している。
一方で、放送のコンテンツを生み出す力は劣っている訳ではない。少なくとも、100年間にわたって番組を作ってきたノウハウの蓄積はあり、それを今後も大いに生かしていってほしいと思う。放送の役割は、その意味で、変わる部分と変わらない部分がある。
―しかし、若い人のテレビ離れは放送にとって深刻な問題だと思うが
何をもって若者のテレビ離れというか、私は正確には若者のテレビ電波離れだと思っている。むしろ深刻なのは「若者のNHK離れ」。確かにNHKの「映像の世紀」などの番組を授業で見せると学生は「すごい」というが、学生は見ていない。朝ドラや、大河ドラマもいろいろ話題にはなるが、話題にするのは高齢層であり、学生は見ていない。
一方で、Tverなどを通じて、学生はテレビ由来だと意識していないまま、民放のコンテンツを見ている。その意味で、若者の「テレビコンテンツ離れ」は進んでいない。伝送路が多様化しているが、見たいコンテンツは見ている訳で、放送局のソフト制作工場という点では、若い人たちに対しても、その役割を今も果たしているともいえる。

―この先、放送はどう生き残るのか、また生き残ることは出来ると思うか
経営面だけ見れば、NHKも民放も、そう簡単には無くなることはないと思う。ローカル放送局は大丈夫かという声も聞くが、多くの放送局は、これまでの内部留保の蓄積があり、経営的には生き残る余力はあると思う。
ただ、キャッシュフロー面から見ると、NHKでは最高裁で受信料の契約義務が認められたとはいえ、この先、若い人は次第に受信料を払わなくなるだろう。家にテレビがなく、スマホだけの人からから受信料を取ることも現実的には難しいと思う。民放も、今回のフジテレビの問題で明らかになったように、広告収入の財源しか持たないことの脆弱性が明らかになった。そうした中で、今後、どう経営を考えていくか難しい課題を抱えている。
―この先の放送局の経営の行方をどう見ているか
民放でいえば、日本テレビ系列4社が認定持株会社のもとで経営統合したが、他の系列には、それぞれに異なる事情や特色があり、同様の対応は難しいと思う。ローカル局は現在、自社で独自番組を制作する自社制作比率が、10%程度で、残りはスポンサーが付いたキー局や準キー局からの番組や、映画の購入など、自社制作番組以外で埋めている。そうしたローカル放送局の今後の選択肢は、二つしかない。一つは、完全に中継局となって、キー局や準キー局の番組をそのまま流すだけの役割に徹すること、もう一つの選択肢は、自社制作の比率を上げていくかだ。
―ローカル局はどうなっていくとみているか
キー局の完全な中継局となることは、ある意味で楽だが、全国に系列局があるのは、特に選挙と災害報道のためには地元に根付いた取材体制が必要だからだ。このためにもネットワーク体制は維持せざるを得ず、ローカル局が完全な中継局になるのは簡単ではない。
一方で、自社制作比率を上げると当然コストがかかる。基本的に各県に4局の放送局があり、ローカルスポンサーの奪い合いとなるほか、地域での人材確保も難しく、課題は多い。
ラジオ局については、いま進めている経費のかかるAMラジオをFMに転換していけば、番組制作にテレビ程のコストはかからないため、生き残る道はあるかと思う。しかし、FMに転換するにも整備にコストがかかり、これも簡単ではなく苦難の道といわざるを得ない。
先ほど話したように、放送局は経営的には終えんはしないが、経営が維持できている間に、どういう選択肢を選ぶかが問われている状況だ。
―日本の放送局の体制はどういう形になっていくと思うか
全国放送のNHKと地域放送の民放、公共放送のNHKと商業放送の民放という二元体制があるが、今後は、全国放送はNHKが担い、民放は地域ごとに地域の番組やニュースに特化した役割を担い、両者で役割分担をする形で行くというのも選択肢だと思う。経営的には、
全国一社民放という形がありえるかどうかだが、ローカル局が黒字のうちであれば統合の可能性もあり得るが、赤字になれば株主から反発を受け統合も難しくなるだろう。
―放送波を使った仕組みとしての放送の今後はどう見るか
電波を使った放送の仕組みは効率的という意味では大変優れたシステムだと思う。システムの維持に経費がかかるのは事実だが、NHKと民放が共同で設備を維持する工夫も進んでいる。また、放送の地上デジタル化から20年たち、マスター設備の更新時期に来ているが、以前に比べ、価格も低下している。更に、公共インフラの維持という観点から、国が協力する部分もある。そう考えると、放送の仕組みは維持出来るのではないかと思っている。勿論、厳しいことは厳しいが出来ない話ではない。
NHKと民放で電波を発射するハード会社とソフト会社に分離する、いわゆるハード・ソフト分離の考えもある。その意味では、今後も放送という仕組みは維持されるのではないか。
―放送はインターネットとどう関わっていくべきか
伝送路が多様化している以上、放送局もネットを使わざるを得ないだろう。伝送路の多様化は、売り場面積が広がったと考えた方がいいと思う。ユーチューブの広告費が5兆5,000億とも言われている。それを使わない手はない。ネットの配信会社がローカル民放も含め企画募集しているなど産業構造も変わっている。そうした伝送路の多様化に対応し財源も多様化していくことは、電波での放送を維持するためにも必要なことだと思う。
―ネットに出ていくことで放送の質は低下しないか
インターネットの適正化の動きはある。ネット自身も、今のままでいいのか、このままでは成長が止まってしまうという危機感がある。行政としても検討が始まっている。
放送サイドがちゃんとしていれば、「良貨が悪化を駆逐する」効用もあり、放送がネットに出ていくことは悪い話ではない。そうやって放送が持つコンテンツ制作力をネットの世界でも生かしていければ、コンテンツ産業全体を良い方向に進める力ともなる。そうしたNHKや民放への期待もある。
―一連のフジテレビ問題をどう見ているか
この問題は、メディア業界全体の「オールドボーイズの問題」と見ている。高齢の男性だけで物事を決めることに根源的な問題があったのではないか。これは、民放もNHKも基本的に同じ。一般企業は、ここ10年で完全に変わったが、放送の世界は残っている。放送が、この先、生き残るうえでは、そこが変われるかが鍵であり、変われなければ次のステージはない。なぜなら、若者から選ばれなくなるからだ。
―ある種共通の課題があるということか
フジテレビ限らず、次の時代に生き残るためには、古い経営体質を変えることと、もう一つは、社会的弱者に向けた番組作りや報道が出来るかどうかだと思う。かつて、フジテレビに対して弱いものいじめではないかとの批判があった。またNHKの1980年代の報道は、国会や行政ネタが常にトップだという調査結果を記した研究もある。それが必ずしも悪いとは言わないが、もっと社会的に困っている人のために注力する放送に変わることが必要だ。この二点が問われている。
-最後にNHKの今後について
この先も、公共放送の役割自体は変わらない。世界で唯一の「放送技術研究所」もあるNHKは、その役割を果たしていってほしいと思う。ただ、今のNHKは、子供の頃には「おかあさんといっしょ」を見るが、その後はテレビを見ず、家庭を持ち、子育てに入って再び子供と一緒に見る。視聴が中抜けになっているのが以前よりの課題。いったん見る習慣が途絶えると、視聴されなくなる。そうなれば公共放送の役割を果たせなくなる。
ネットの法改正も行われたが、10年前にNHK自身が思い描いていた中身とは、大きく変わってしまった。本当はネット独自サービスを認めるべきだったと思う。例えば、国民の財産でもある番組のアーカイブをネットを通じて活用することなどもやって欲しい。とにかく、若い人がチャレンジしたい思える組織、トライする人を受け止める組織として、経営と番組をしっかりしてほしい。
この記事を書いた記者
-
営業企画部
営業記者 兼 Web担当
新しいもの好き。
千葉ロッテマリーンズの応援に熱を注ぐ。
最新の投稿
本企画をご覧いただいた皆様からの
感想をお待ちしております!
下記メールアドレスまでお送りください。
インタビュー予定者
飯田豊、奥村倫弘、亀渕昭信、川端和治、小松純也、重延浩、宍戸常寿、鈴木おさむ、鈴木謙介、鈴木茂昭、鈴木秀美、
西土彰一郎、野崎圭一、旗本浩二、濱田純一、日笠昭彦、堀木卓也、村井純、吉田眞人ほか多数予定しております。
(敬称略:あいうえお順)