
古野電気、魚群探知機が「IEEE Milestone」認定(1)
古野電気(兵庫県西宮市、古野幸男代表取締役社長執行役員)は1949年に世界で初めて魚群探知機を商品化し、水産業の近代化に貢献したとして世界最大の電気・電子分野の国際専門組織IEEEから「IEEE Milestone」の認定を受けた。4月25日に国内外から、キャスリーン・クレイマー会長をはじめ、トム・コフリン前会長、福田敏男・元会長などIEEEの関係者が多数来社し、同社西宮本社にて贈呈式が執り行われた。「電波タイムズ」では、古野幸男代表取締役社長執行役員に「IEEE Milestone」認定の感想と商品化へのエピソードなどを聞いた。
――世界で初めて商品化した魚群探知機が「IEEE Milestone」に認定されました。今のお気持ちをお聞かせください
「世界的に著名な専門組織IEEEから表彰を受けたことは、たいへんありがたいことだと感じました。1948年(昭和23年)に魚群探知機が誕生して既に77年です。漁業界に革命を起こした画期的な商品だったからこそ、このような賞をいただき非常にありがたいと思っています」
――魚群探知機の実用化に関して、当時のエピソードなどお聞かせください
「最初に魚群探知機のお話をします。魚群探知機のルーツとなるものは軍の払い下げ品である音響測深機と呼ばれる機械で、簡単にいうと音波によって水深を測る装置です。戦後、古野電気の創業者である義父(古野清孝)が海の底を計測できるのなら、もしかすると海中の魚群も探知できるかもしれないとひらめいた―これが魚群探知機が誕生したきっかけです。昭和23年頃は、食料不足で困っていた時代で、タンパク質の源となる魚もなかなか食べられない。当時は、漁師が経験と勘で網を巻いていました。これでは当たる確率が低く、魚がいるとわかった上で網を巻くこととは大きく違います。そしてすぐ下の弟(古野清賢)と一緒に1年半ほどかけ、ついに魚群探知機に用途転換しました。漁業界で電子機器を初めて導入して一種の革命を起こした商品となりました」
――実証実験のようなことは行なったのですか
「魚を見つけることはできるのですが、網を巻くには魚は動くし、海は流れるし、船も動く。網をどう巻き、どう絞り、どのようなタイミングで巻き上げるかのノウハウは私達にはなかったわけです。お客様は機械を買うのではなくて、機械の効果を買うのです。魚群探知機を買っていただいても、本当に魚が獲れるかが最も肝心なところですので、最初にご協力いただいた漁師さんからは獲り方をお聴きし、そのノウハウを咀嚼して理解していきました。新しいお客様には魚群探知機の映像を見ていただき利用する際のノウハウまでをセットとしてお伝えしました。それが早い時期から普及していった大きな理由だと思います。販売面では主要な漁港に我々の営業所を設けて、取り付けをする技術スタッフとペアで直接、お客様と接触して理解していただきながら進めました」
この記事を書いた記者
- 元「日本工業新聞」産業部記者。主な担当は情報通信、ケーブルテレビ。鉄道オタク。長野県上田市出身。
最新の投稿
 CATV2026.01.10イッツコム、防災活動の功績で青葉消防署から感謝状
CATV2026.01.10イッツコム、防災活動の功績で青葉消防署から感謝状 CATV2026.01.09イッツコム、アートラッピング電車特番
CATV2026.01.09イッツコム、アートラッピング電車特番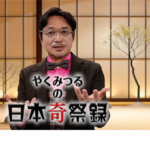 CATV2026.01.08日本デジタル配信、新番組「やくみつるの日本奇祭録」
CATV2026.01.08日本デジタル配信、新番組「やくみつるの日本奇祭録」 CATV2026.01.08イッツコム「おうち防災スタートセット」
CATV2026.01.08イッツコム「おうち防災スタートセット」


