
古野電気、魚群探知機が「IEEE Milestone」認定(2)
――魚群探知機の原理はどうなっていますか
「魚群探知機は、船底に穴を開けてそこに取り付けます。一番肝心なセンサー、振動子は船底に設置します。センサーと演算装置と表示器での3点セットで信号を電気処理します。船底に開けて固定化している理由は泡にあります。泡の影響が一番少ないところが船底で、超音波信号というのは異質なものがあると反射してしまいます。水の中や空気中も超音波は通ります。ただ、水中の泡のように液体と気体が混ざっていると液体は通過しても気体で反射してしまいます。船が走れば泡が出ますので、泡の影響が大きいところにセンサーを置いても超音波がうまく魚群に届かないのです。これも実際に船に付けた時にどういう課題があるか、お客様と一緒に悩みながら解決してきたことのひとつです。こうした繰り返しで魚群探知機がお客様にとってほんとうに価値がある商品になってきたのです」
――1938年(昭和13年)に古野清孝さんが長崎県口之津町(現在の南島原市)に古野電気の前身である「古野電気商会」を創業しました。その当時のお話もお聞かせください
「口之津は島原半島の南端にある大きな港町です。三井三池炭鉱(福岡県大牟田市)の石炭を有明海を通して運ぶ際、口之津で積み替えて上海や関西の方に持っていく。有明海はあまり波がないので、小舟で運んで口之津で大型の機関船に積み替えていました。昭和の初めの大恐慌で義理の父親(古野清孝)がラジオの真空管などの修理をやりはじめて、先の戦争が激しくなって三菱重工業長崎造船所(長崎市・諫早市)が盛んになった頃にはラジオの修理から船の電気工事に切り替えて、弟(古野清賢)も一緒になって苦しいなりにも収入を得て、生活していた。そして、戦後見つけた音響測深機を魚群探知機に転換し、本格的に販売を開始しました」
この記事を書いた記者
- 元「日本工業新聞」産業部記者。主な担当は情報通信、ケーブルテレビ。鉄道オタク。長野県上田市出身。
最新の投稿
 CATV2026.01.10イッツコム、防災活動の功績で青葉消防署から感謝状
CATV2026.01.10イッツコム、防災活動の功績で青葉消防署から感謝状 CATV2026.01.09イッツコム、アートラッピング電車特番
CATV2026.01.09イッツコム、アートラッピング電車特番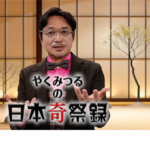 CATV2026.01.08日本デジタル配信、新番組「やくみつるの日本奇祭録」
CATV2026.01.08日本デジタル配信、新番組「やくみつるの日本奇祭録」 CATV2026.01.08イッツコム「おうち防災スタートセット」
CATV2026.01.08イッツコム「おうち防災スタートセット」


