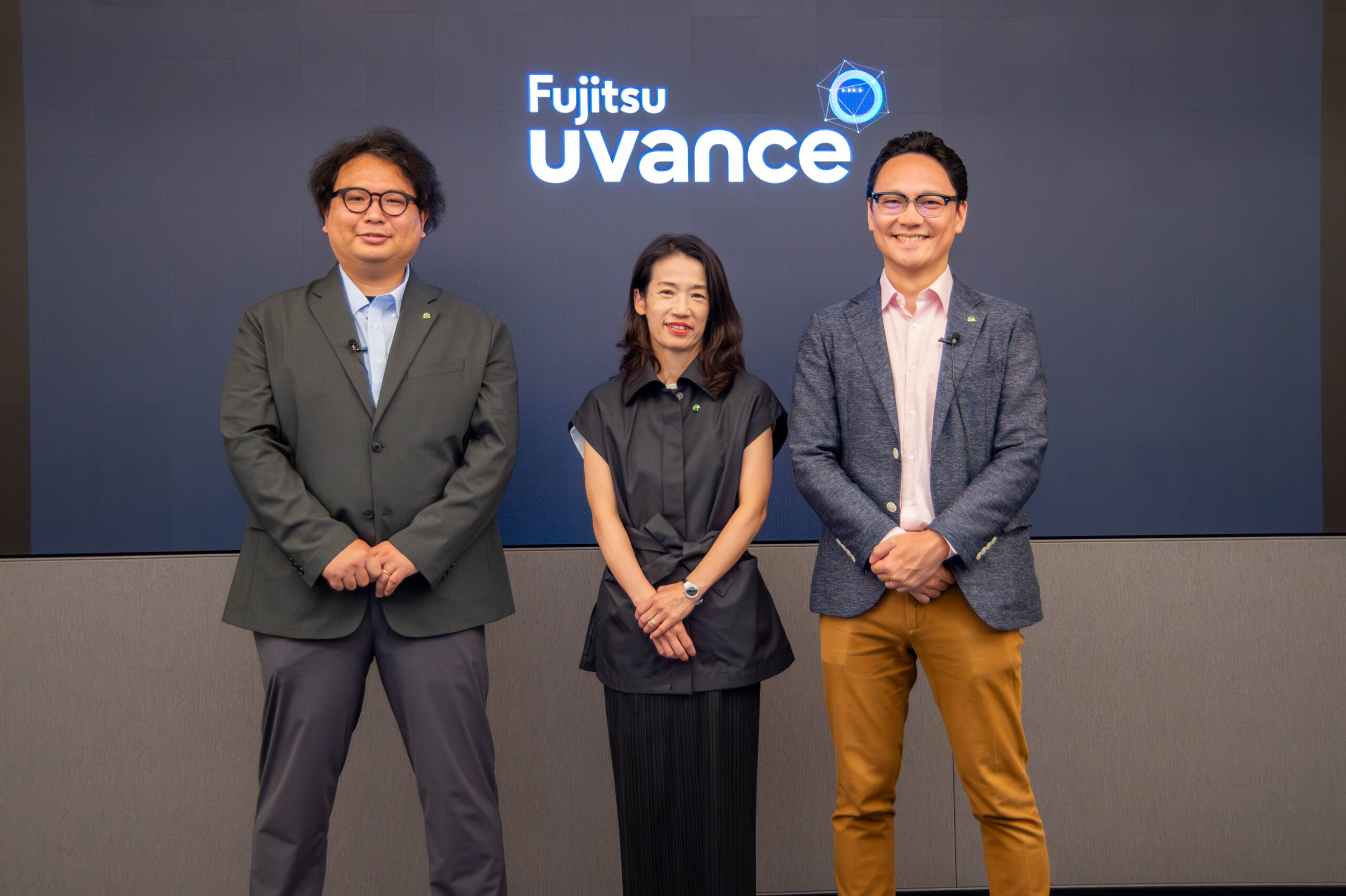
富士通、ヘルスケア業界で安全かつ効率的にAIを活用できる基盤
富士通は、データとAIによって医療機関の経営効率化と安定的な医療サービスの提供を加速するため、ヘルスケア業界において安全かつ効率的にAIを活用できる基盤を、社会課題を起点とする事業モデル「Fujitsu Uvance」の「Healthy Living Platform」上に構築した。8月27日に「Fujitsu Technology Park」(川崎市)で記者説明会を開催し発表した。
◇ ◇ ◇
同基盤には、オーケストレーターAIエージェント(様々なAIエージェントの連携を支援し全体統括を行うAIエージェント)が実装されており、富士通および国内外のパートナーが開発する多様なヘルスケア特化型AIエージェントを柔軟に組み込むことが可能となる。これにより、世界最先端の医療業務オペレーションの早期実装に貢献することで、日本のヘルスケア業界における業務改革と持続可能性の向上に貢献する。
◇
富士通執行役員常務グローバルソリューション(ソーシャルソリューション&テクノロジーサービス担当)の大塚尚子さん、クロスインダストリーソリューション事業本部Healthy Living事業部長の荒木達樹氏、同シニアディレクターの勝田江朗氏が「Healthy Living」における新たな取り組み「ヘルスケアAIエージェント」の説明をした。また、戦略的パートナーシップを組むエヌビディア合同会社エンタープライズ事業本部事業本部長の井﨑武士氏がNVIDIAが推進するソブリンAIと富士通とのコラボレーション」で説明した。
東京大学医学部附属病院循環器内科特任講師の小寺聡氏が「ヘルスケアAIエージェントへの期待」で説明した。
大塚さんは、日本の医療提供体制が抱えている課題として厚生労働省の調べで平成27年度の国民医療費は約47兆円、医療機関の支出における人件費の割合は約43%、人件費における事務作業は約3兆円に達すると指摘した。また、日本病院会の調べで経営赤字を抱える医療機関の割合は75%であり、厚生労働省の調べで約4割の病院常勤勤務医の時間外勤務は1年間で960時間にもなると提示した。
そして、「『Fujitsu Uvance』は、データとAIで高度な意思決定を実現し、ビジネスインパクトとソーシャルインパクトを両立することを目指している。今回、『Fujitsu Uvance』が挑む領域は、まさに今、持続可能性の危機に直面している日本の医療である。今後、少子高齢化が進むと患者数は増大して、この状況の加速が懸念されている。これらの課題のもたらす要因は様々あるが、中でも複雑で属人化した医療業務オペレーションにより膨大な業務作業が発生しているのが要因と私たちは見ている。今回、富士通は、ヘルスケア業界において安全かつ効率的にAIを活用できる基盤を構築した。この医療業務オペレーションを先ほど申し上げたデータとAIにより、簡素化することで医療従事者を解放することが、医療機関の業務経営変革につながるし、日本医療の持続可能性を向上していくことになると考えている」と話した。
◇
続いて、荒木氏は次のように説明した。
複雑かつ属人化した医療業務オペレーションを改革して、医療従事者をそこから解放するためには、医療従事者に代わって、具体的な指示がなくても、特定の目標達成のために状況を正しく認識し、必要なタスクをこなしていく代理人のような存在が必要となる。これがAIエージェントである。ヘルスケアに特化したAIエージェントが、信頼性の高い基盤の上で、お互いに協働し合いながら、日本の医療提供体制の持続可能化に取り組んでいく。この富士通が創ろうとしている世界の一端のポイントは次の通りだ。
持続可能性の危機に瀕する日本の医療がAIエージェントの力で変わる。富士通は、ヘルスケアに特化した AIエージェントの実行基盤を構築する。従来、医師や看護師、医療事務などの専門職が行っていた業務は、業務特化型AIエージェントが担う。さらに、司令塔であるオーケストレーターAIエージェントの指示の下、自律的にAIエージェント同士が連携、協働することで、各業務の効率化にとどまらない組織全体の最適化が進む。
いずれは病院という施設の枠も超え、より広範、多様な環境に広がり、時間や場所にとらわれない新たな医療提供体制が作られる。例えば、医療現場では、AIエージェントが、受付、問診、文書作成などの間接業務を代行することで、医療従事者がより診療や患者ケアに専念できるようになる。
医療機関では、間接業務をAIエージェントが担うことで人件費が最適化され、収益性と経営の持続可能性の両立につながる。そして、患者はAIエージェントにより医療へのアクセス方法が多様化することで、一人ひとりの状態や背景に合わせた最適な医療サービスを適切に受けられるようになる。
AIエージェントが人間のバディーとなり、日本医療の未来を開いていく。この世界を作るには、多岐にわたる医療業務のオペレーションの全体を変えていかなければならない。
富士通は長年、医療情報システムの提供を通じて、医療業務オペレーションについての知見を蓄積し、またその過程で多くの医療機関の皆様と協働してきた。それらを基に、まずはこのヘルスケア領域におけるAIエージェントを安全かつ効率的に実装できる基盤をヘルシーリビングプラットフォーム上に構築する。
基盤の中には、データの構造化を担うAIエージェントや総合運用監視を行うAIエージェント、さらにはこの業務特化型のAIエージェントが様々な形で連携をしていく。その連携をサポートするための全体管理を行うオーケストレーターAIエージェント、これらが実装されていく。
この基盤を国内外のパートナーに提供することで、より多くのより多様なAIエージェントをいち早く社会実装することで、広範かつ迅速に医療業務オペレーションの変革を進める。
さらに荒木氏は、この様々なAIエージェントが実装される基盤、こちらについてはNVIDIAの支援により構築をしている。これまで富士通が培ってきた医療業務オペレーションの知見、それにアクセラレーテッドコンピューティングやAIエージェントの基盤技術において世界をリードされるNVIDIAの支援、これらを組み合わせることで、世界最先端の医療業務を、日本にもたらすことを可能にする―とまとめた。
◇
エヌビディア合同会社エンタープライズ事業本部事業本部長の井﨑武士氏が次のように説明した。
ソブリンAIという言葉は、日本語で言うと主権ということで、これを解釈して、自国の、もしくはある組織という形で、そこに特化した、AI、LLMといったものの必要性を打ち出したものだ。
このソブリンがなぜ必要なのかだが、例えば通常の基盤モデル、ほとんどが北米であったり、もしくは中国等で開発をされているが、そうするといわゆる文化背景というものが全く理解されていないものが多くなってしまう。日本のデータを活用しながら日本の文化背景にきちんと合わさって様々な応用範囲、そういったアプリケーションに特化したソブリンAIモデルが必要である。
当然ソブリンデータということになるので、こういったデータを最新に更新しながら学習をし続けることによって、最新のデータを使って、そういった業界と企業と関わった、もしくは国に特化したモデルを活用していくところになる。
これまで富士通とは非常に長く協業を続けてきた。スーパーコンピュータへの協業であったり、もしくはそれに関するシステムインテグレーションの協業が続いてきたが、最近ではいわゆる我々が持っているソフトウェア技術を活用いただいている。
新たなエージェントというのも生まれてきて、このAIの進化は、2020年のチャットGPTを起点として始まったこの流れから、今年はAIエージェント元年と言われているが、こういったいわゆる様々なエージェントを横連携しながら、必要なツールを使いながら自律的なエージェントはこれからどんどん広がっていって、社会産業を大きく変えていくと信じている。
こういったものは自律的にはどういった動きをしなければいけない、判断をしなければいけないとなると、エージェントは非常に重要な技術になってくる。こういった進展の中でですね、まさに富士通とエージェントという中でヘルスケア領域に手を組み始めたので、これから、富士通ともっと先の協業も含めて新しい未来を創造していこうと考えている。
◇
続いて、シニアディレクターの勝田江朗氏が次のように述べた。
勝田氏は実際の利用シーンをスクリーンに映しながら説明した。
AIエージェントが受付し、必要な項目の問診を行い、適した診療科へ案内する。患者との会話を通じて、受付、問診、診療科分類の3つのAIエージェントと、総合的な判断を行うオーケストレーターAIエージェントが連携し、自律的に処理を進める。
実用シーンで、中核となるのが指令等の役割も果たすオーケストレーターAIエージェントで、これは、患者データや医療業務データなどと同様に、問診や診療科分類といった専門スキルが必要なタスクで最適な業務特化型AIを選択する。この動きを自律的に行う高度な仕組みを備えた。
また、これらのAIエージェントが動作するためには、もととなるデータがきちんと整備されていることが必要になる。その基盤は、かつてないほど膨大な情報が価値を形に変換するデータ構造化、データ化するにあたっての個人情報の流用等を含むコンプライアンス管理、安全に利用するためのセキュリティ。これらのシステム間でのデータ交換を簡単にする統合運用性も備えている。これらは、単なる業務システムの構築スキルだけではなく、各専門職がおこなう医療業務の能力、それぞれの実務で扱う情報の関係性を高度に定義できる技術だからこそ、実現できたものだ。私たちは今後この強みを活かして、ヘルスケア向けAIエージェントの実装に取り組む。
◇
続いて、東京大学医学部附属病院循環器内科特任講師の小寺聡氏が「ヘルスケアAIエージェントへの期待」で説明した。
私は、医療業務に並行して様々な医療AIを開発している。例えば心臓の超音波検査があって心臓の動き方を観察する検査になるが、心臓の超音波動画を採って、検査した後に、結果のレポートを作る必要がある。この作業をAIでできるように、動画とレポートの類似度から、レポートを生成するAIを完成させた。こういうAIがあると、医師がレポートを書くサポートになるので、我々にとっては、非常に有用だと思っている。その他に、冠動脈造影検査のレポートを作成するAIも開発した。狭心症、心筋梗塞で心臓を取り巻く血管を、造影検査を行って、白黒画像を撮るわけだが、動画から重要な静止画を切り出してくるAIをまず作って、それに病歴を一緒に入れると、所見文と、検査が終わった時に、レポートを生成する。
AIも我々の業務支援になるのではないかと期待している。AIが現場に入ってくる上では、UI、ユーザーインターフェースも重要だと思っている。
続いて画面にあるのは自身のアバターで医療シーンを行う場面だ。私自身はよくできていると思うが、気持ち悪いという方もいるので、AIが現場に入ってくるためには、インターフェイスも工夫していく必要があると思う。
次にエージェントへの期待について。我々様々な業務を行っていて、どうしても患者さんに割く時間が限られてしまう。そういった中で、問診や文書作成をエージェントがサポートしてもらえると、我々が患者に、専念できる時間を確保できると思う。我々だけ、医療従事者だけではなくて患者さんにもメリットがあると思う。業務が効率化されていくと患者さんの待ち時間が短縮されると期待している。時間と空間にとらわれない医療の実現もできると期待している。一方で、医療の情報で正確性の問題があると思う。問診で収集した情報に誤りがあると、その後の診療全体に影響してくる。医療情報は、個人情報の塊なので、セキュリティー、安全性も非常に重要だ。
AIエージェントが現場に入ってくる際に、ワークフローについても考える必要があると思う。非常にいいものだが、ワークフローをうまく抱えて現場に投入していかないと、かえって邪魔が増えたということも起こり得ると考えている。医療従事者、患者も含めて、これに慣れてうまく適用していかなければいけない。そして、医療従事者として信頼できるインターフェース、機能にしてもらう。
この記事を書いた記者
- 元「日本工業新聞」産業部記者。主な担当は情報通信、ケーブルテレビ。鉄道オタク。長野県上田市出身。
最新の投稿
 CATV2026.01.10イッツコム、防災活動の功績で青葉消防署から感謝状
CATV2026.01.10イッツコム、防災活動の功績で青葉消防署から感謝状 CATV2026.01.09イッツコム、アートラッピング電車特番
CATV2026.01.09イッツコム、アートラッピング電車特番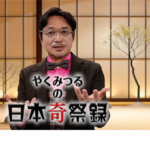 CATV2026.01.08日本デジタル配信、新番組「やくみつるの日本奇祭録」
CATV2026.01.08日本デジタル配信、新番組「やくみつるの日本奇祭録」 CATV2026.01.08イッツコム「おうち防災スタートセット」
CATV2026.01.08イッツコム「おうち防災スタートセット」


