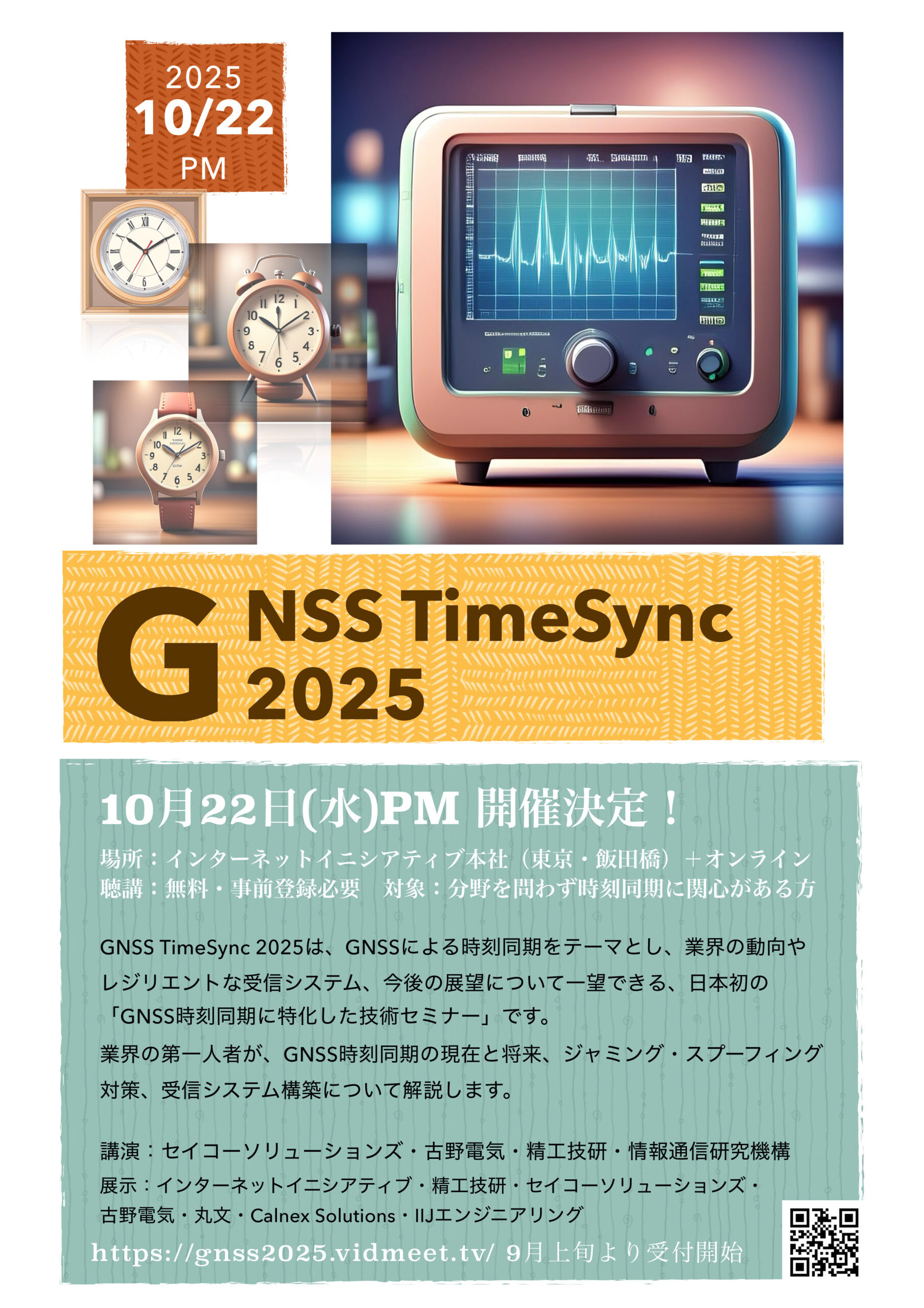
「GNSS TimeSync 2025」10月22日にIIJグループ本社で開催
インターネットイニシアティブ(IIJ)主催の「GNSS TimeSync 2025」(https://gnss2025.vidmeet.tv/)は、10月22日(水)午後2時(開場は午後1時30分)から午後6時まで、IIJグループ本社・飯田橋グラン・ブルームで開催される。共催は精工技研、セイコーソリューションズ、古野電気、丸文、Calnex Solutions plc、IIJエンジニアリング。「GNSS TimeSync 2025」は、GNSSによる時刻同期をテーマとし、業界の動向やレジリエントな受信システム、今後の展望について一望できる、日本初の「GNSS時刻同期に特化した技術セミナー」として企画した。業界の第一人者が、分野を横断しGNSS時刻同期の現在と将来を解説する。
「GNSS TimeSync 2025」の狙いは、NTP、PTPなど時刻同期プロトコルに接する技術者に、その前段となるGNSSにまつわる最新の技術動向を伝えることだ。第一線のメーカや研究機関の技術者・研究者を招いて、講演を行う。放送・通信・金融を含め、時刻同期技術に関心のある人が全てが参加対象になる。
インターネットイニシアティブ、精工技研、セイコーソリューションズ、古野電気、丸文、Calnex Solutions plc、IIJエンジニアリングによる展示ブースを設けている。また内閣府、NICTのコーナーも用意している。
主催者側では「GNSSによる時刻同期に特化したイベントというのは、国内では初めての開催なのではないかと考えています。ラインナップの特徴としては、産官とり混ぜてのセミナーとなっており、さまざまな角度から時刻同期についての話題がお届けできると思っています。まさに2025年の今でこそ語れる・お伝えできる内容ではないでしょうか」としている。
GNSSは、〝Global Navigation Satellite System〟の略。地球上空を周回する衛星群(コンステレーション)から発信される電波を用い、地表上や上空において受信機から現在地などを割り出すことができるシステムのこと。日常的にもカーナビやスマホの位置情報サービスで目に触れることが多い。クルマにはナビが標準装備されている。またスマートフォンの位置情報サービスを使ったサービスは圧倒的に便利で、地図を見るだけにとどまらず「近くのお店や駅」などが簡単に探すことができる。GNSSは、ITサービスの利便性向上の立役者でもある。
GNSSは位置情報を割り出す用途で多く使われているが、他にも提供されている機能があり、総合して「PNT」と呼ばれている。
PはPositioning(測位)、NはNavigation(航法)、TはTiming(計時)である。このうち、航法については、航空機や船舶など、かつては天測等しながら目的地の方角を割り出していたものが、いまや電子的に表示されるようになっている。これが運航の安全に大いに寄与していることは間違いない。しかしGNSSで「計時」とはどういうことなのか。
実はGNSS衛星には高精度の原子時計が搭載されている。その時刻情報は、衛星の軌道情報と共に符号化され、変調され送信されている。受信機では複数の衛星からこれらの情報を得ることで測位できるようになるが、同時に高精度時刻情報も得られることになる。
GNSSで得られる時刻の正確さは100ナノ秒程度になる。GNSS受信機は衛星の起動情報から電波の到達にかかる時刻を割り出すが、この精度は距離に換算すると3メートルである。つまりその誤差を認識できるようになる。この10ナノ秒の精度が何に資するかというと▽放送機器の駆動に必要なクロック▽金融におけるHigh-Frequency Trading▽電力におけるスマートグリッド―といったことが代表的なものとして挙げられる。GNSSは複数の衛星で構成されているが(これを衛星コンステレーションという)、これはすなわち「どこにいても同じ精度で時刻情報を得ることができる」ことに繋がる。広域化・ネットワーク化された産業システムにおいてGNSSが非常に重要なパーツになることは、簡単に想像ができる。
例えば放送業界では映像・音声信号のIPネットワーク化に伴い、高精度な時刻情報を共有する必要が生じた。そこでMedia over IPと呼ばれるシステムは、IPネットワーク上でPTP(Precision Time Protocol)によりすべての機器を同期させるデザインが採用されている。このPTPの供給サーバ(Grand Masterと呼ばれる)は、源信としてGNSSが採用されることが多い。PTP利用は局舎内にとどまらず、例えば本局と中継車の両方にGNSS源信のPTP GMを配置することにより、離れた場所でも同期が取れるようになった(実は、今までは同期していなかった)。またラジオ局では音声伝送のためにINSネットが広く使われていた。INSネットでは機器駆動のために網側よりクロックが供給されており、音声伝送機器もこれに従属することで同期が実現できていた。しかしINSネットの廃止や音声信号のIPネットワーク化に伴い、現在ではやはりPTPが広く使われるようになってきている。
NTP(Network Time Protocol)でも源信としてGNSSが採用されることもある。GNSS受信モジュールがNTPサーバに内蔵され、アンテナ入力端子が付く形になる。なおNTPはPTPよりも時刻精度は緩いため、源信として他の手法(NICTの光テレホンJJYなど)も用いられている。一般ユーザがPCなどの時刻合わせをしたい場合はパブリックなNTPサーバをクライアントとして使うことで問題はないと考えられる。
このように産業界でも幅広く使われるようになった、あるいは、なることが期待されているGNSS時刻同期だが、実はいくつかの課題がある。
現代のITシステムではアベイラビリティの確保が強く求められる。IPネットワークやサーバでは冗長化やクラスタリングなどの技術が幅広く使われており、NTPやPTPでもシステムの冗長化を組むことが可能だ。ところが、NTPサーバやPTPグランドマスタの源信側、つまり受信アンテナ側も含めた形での冗長構成をどうやって組めば良いか、悩む人も多いかと思う。また、近年は一般ビルやデータセンターでのGNSS利用も広がってきているが、アンテナからの配線ルートをどう確保するかも問題になることがある。GNSSの使用する周波数は1.5GHz/1.2GHz/1.1GHzであり、アンテナから受信機までのルートで減衰しないように太い同軸ケーブルを用いる必要がある。たとえば10D-FBの外径は13mm程度。このような太い線を縦坑に通すためには十分な空きスペースが必要で、配線自体が困難であることも少なくない。しかし同軸ケーブルの代わりに電波を光ファイバーで伝達する変換ボックスを用いると、必要なのはシングルモードファイバ1心のみとなり、配線スペースの大幅な削減が可能になる。
「GNSS TimeSync 2025」参加者募集中
このセミナーは「会場参加」または「オンライン参加」を選択できる。オンライン参加希望者は開催前日までにURLを送付する(Web経由で全国どこからでも視聴できる)。参加費は無料(事前登録制)。対象は分野を問わず時刻同期に関心がある人。
セミナー開催場所は、東京都千代田区富士見2丁目10番2号 飯田橋グラン・ブルーム。電車でのアクセスは▽東京メトロ有楽町線、東京メトロ東西線、 東京メトロ南北線、 都営地下鉄大江戸線飯田橋駅[B2 a出口]徒歩2分、あるいは飯田橋駅[A4 出口]徒歩4分▽JR総武線・中央線 飯田橋駅[西口]徒歩1分。
参加申し込みは次のURLで。
https://biz.iij.jp/public/seminar/view/40383
この記事を書いた記者
- 元「日本工業新聞」産業部記者。主な担当は情報通信、ケーブルテレビ。鉄道オタク。長野県上田市出身。
最新の投稿
 CATV2026.01.10イッツコム、防災活動の功績で青葉消防署から感謝状
CATV2026.01.10イッツコム、防災活動の功績で青葉消防署から感謝状 CATV2026.01.09イッツコム、アートラッピング電車特番
CATV2026.01.09イッツコム、アートラッピング電車特番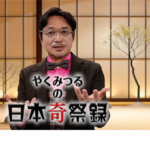 CATV2026.01.08日本デジタル配信、新番組「やくみつるの日本奇祭録」
CATV2026.01.08日本デジタル配信、新番組「やくみつるの日本奇祭録」 CATV2026.01.08イッツコム「おうち防災スタートセット」
CATV2026.01.08イッツコム「おうち防災スタートセット」


