
【独自】NECと東京科学大学、バーチャル医療・ヘルスケアシステムで協定
NECと国立大学法人東京科学大学(東京都目黒区、大竹尚登理事長、田中雄二郎学長)は、患者中心の医療と医療従事者の能力を最大限に発揮できる業務環境の実現に向けて、仮想空間上で医療関連データの流通を可能とするバーチャル医療・ヘルスケアシステム構築に関する協定を締結し、研究開発を開始した。またこの取り組みを推進するため、医療関連の研究者や、スタートアップから大手まで様々な企業を対象とした共創コミュニティを2025年度内に立ち上げる。「電波タイムズ」では、両社が描く〝ヘルスケア・ライフサイエンスの未来〟について、NECの医療ソリューション統括部プロフェッショナルの小関将和さんに話を聞いた。
厚生労働省による地域医療構想や地域包括ケアシステムなどの政策により、複数の医療機関や様々な医療・介護制度に跨ったサービスの提供が始まっている。しかし、疾患毎に異なる診療プロセスや見守りを患者中心で行うための情報管理の仕組みは整備されておらず、また患者中心の医療・ヘルスケアサービスに必要な要素技術・サービスに関わる新規スタートアップの創出や、優れたアイデア・技術を有効活用する方法も求められている。
NECと東京医科歯科大学(現・東京科学大学)は2020年10月に、「ヘルスケア領域における新たなサービス事業の創出・推進に関する連携協定」を締結し、一人ひとりの健康状態に合わせた身体のケアサービスを提供する「NECカラダケア」の運営や、AIによる慢性腰痛のセルフケア支援技術の開発などを行ってきた。両社は24年3月、AIにより慢性腰痛のセルフケアを支援する技術を開発したと発表した。スマートフォンで在宅でも迅速に原因を推定し、改善運動を推薦するソリューションだ。
取材したNECの医療ソリューション統括部プロフェッショナルの小関将和さんは「今回の発表前から東京科学大学と取り組んでいたのが『病気にならないためのヘルスケア』の実現です。研究・事業両面で具体的成果を得ながらその深化を目指してきました。役割としては、NECはAI技術および事業に関わるデジタル基盤を手がけ、東京科学大学はAI技術等の開発、サービス内容の科学的な品質の確保・向上のために必要な研究及び人材育成等のサポートを行い、両者で全体の事業スキームを検討しました。手を組んだ成果のひとつが実証店舗『カラダケア』(東京都新宿区)です。東京科学大学のサポートを受けています。セールスポイントは〝ひとと技術であなたの健康に寄り添います。肩・腰などに不調を感じる人に、カラダの専門家である理学療法士が一人ひとりに合った施術を行います〟。保険適用外ですが、当店所属の理学療法士資格を持ったセラピストが施術を行います。病気になる前に、いかに健康な状態を保つか。理学療法士と一緒になって未病対策を進めています」と話した。
予防医療の意義は、急性期になって患者が病院にかかる手前の段階から、いかに患者さんを良い状態に持っていくか。それが医療リソースの逼迫であったり医療費の高騰を防ぐなどにも効果があるという。
小関さんは「NECは、2025年に向けた中期経営計画で『ヘルスケア』を注力領域のひとつに挙げています。もともと医療データは、病院ごとに管理して、しっかりしたセキュリティのもと決して外部には出さないものです。しかし、今はそこをいかにシームレスに有効活用していくか、そういう時代に入ってきました。自分のデータが他の人のために役立って、さらに次の人の役に立つ、そういった世界を作っていきたいと考えました。当時の東京医科歯科大学とは共同研究を行い縁が深かったものですから今回の協定締結となりました」と述べた。
そして東京医科歯科大学、東京工業大学、NECの3者連携を発展させ、NECが有する最先端AI技術や医療情報システムの構築およびサービス提供ノウハウと、東京科学大学が有する医療・ヘルスケアの知識や工学的知識を融合し、バーチャル医療・ヘルスケアシステムを構築する。これにより、予防医療から急性期、慢性期、介護までをシームレスに繋いだ疾患毎に異なる患者中心のサービスや、医療従事者の能力を十分に発揮できる業務環境の実現を目指す。
「ヘルスケア領域での医工連携による新たな価値創造・事業創造を目指し、産学連携での検討を3者で行います」(小関さん)。
病院内・外に存在する医療・ヘルスケア情報への容易なアクセスと安全な情報共有を実現するデータ基盤や、データ収集用デバイスの開発などを行う。また将来的には、蓄積したデータを製薬企業や医療関連のセンサー開発企業などに提供する事業も検討する。
同取り組みを推進するための共創コミュニティを25年度内を目標に立ち上げ、医療関連の研究者やスタートアップ企業に、研究フィールドや企業とのパートナリングおよび市場・顧客へのアクセス機会を提供するなど、効率的な事業参入を支援する環境を整備する。
「データ収集でお話しすると治療データ収集・解析では、東京科学大学は大きな附属病院を持たれており様々なデータが集まってきます。今後予定しているサービスが立ち上がって、循環し始めると、データがさらに蓄積されてきます。さらにデータを活用したい方々に使っていただくために、医療従事者の方々が物事を判断したり、何かわからないことがあったときにそのデータを活用するというのはもちろんですし、その医療従事者以外にも、スタートアップ企業で特定の疾患に向けて何かサービスを始めたいプレーヤーにもデータを利活用してもらう、それが将来的なポイントとして考えています。NECでも東京科学大学でもない、新しいプレーヤーの方々をどんどん引き込んでいくようなコミュニティの機能を持たせたいと思います。東京科学大学の中からもスタートアップが生まれてくるでしょう。そうした学内ベンチャーもコミュニティの中に加わって頂ける可能性があると思います」と話した」(小関さん)。
◇
次に、具体的な取り組みを聞いた。ひとつ目は『ウェラブルデバイス活用によるSLE疾患(自己免疫性疾患)の病態可視化』である。SLEは全身臓器に炎症を生じる自己免疫疾患で、寛解(症状がない状態)と再燃(症状の悪化)を繰り返しつつ臓器障害が累積する。寛解から再燃に至る前兆期に治療介入することで発症を予防可能とすることを目指して、臨床情報+ライフログによるデジタルバイオマーカーの開発に取り組む。
小関さんは「これはウェアラブルデバイスで心拍や体温といったバイタル情報を取りながら、SLE疾患の症状をご自分で自覚できるようにするものです。SLE疾患は特に自覚症状が薄いので、患者さんは毎朝起きて今日はどういう状態なのか自分自身ではわからないと聞きます。不安で病院に行って、医者もいろいろなデータを見るのですが、すぐに病態の判断がつきにくいとも聞いています。そこでデジタルバイオマーカーを開発して、様々なデータをどんどん取り込んで、今は症状が少し悪化に向いているようだから、早めに医療機関にかかりましょうとか、今は活動期ではなく寛解期に入っているようなので、安心して1日を過ごしてくださいなど、日々の様子が分かるものがつくれないかと取り組んでいます」と話した。患者も医療従事者もなかなか気付けなかったところを、バイオマーカーがサポート。ある値が示されたら医療機関にかかって、より悪化して自覚症状が出る一歩手前で防ぐことができればよいと小関さん。
◇
具体的な取り組みの2つ目は『医療的ケア児の成長と家族の時間を見守る多職種データプラットホームの共創』である。医療的ケア児の養育において、絶え間なく個別性の高いケアを求められ、親が抱える負担が大きいことから、「子どもをケアする時間」を「子どもの成長を喜ぶ時間」へシフトさせる仕組みの構築を目指す。
小関さんは「医療的ケア児とは、自分で自分の意思をうまく発せられない子供たちです。医療的ケア児を抱える親御さんは、基本的に子供のケアにほとんどの時間を費やしています。そうした親御さんは子供の睡眠時、数時間おきに起きてケアするのが身体的な疲労につながっています。そうした方々に『少しでもケアの負担を軽減したい』との思いがありました。具体的には『日常的なケアデータを自動収集し、熟達した個別ケアのノウハウを再現できる医療機器の開発』を目指しています。例えば、子供の呼吸パターンを評価して、自動で体位変換を促すベットなどです。お子さんごとに気をつけなければいけないポイントや、何時に何をしなければいけないなどが異なるので、このお子さんは、こういうケアが必要だということをデータで〝見える化〟して、親御さん以外の保育園の職員や学校看護師らが日々のケアをできるような形にしたいと考えています。少しでも親御さんの負担を減らしてあげたいと。親―学校(保育園)―医療従事者(学校看護師)をつなぐ情報システムの構築に取り組んでいきます」と話した。
◇
具体的な取り組みの3つ目は『整形リハビリテーションのデジタル活用に向けたAI技術に関する研究』である。AIによる動きのデータ収集を強化。理学療法士のスキル・ノウハウをオンラインで届け、時間・空間的な制約を排除する取り組みだ。
2025年度は『データ収集強化・精度向上』として▽姿勢状態認識のロバスト性(外部環境の変化に影響されにくい性質)向上や、数値化によるラベル精度向上を進めている。例えば『姿勢状態認識』で、前屈している人をスマートフォンで撮影し、そのカメラの角度を自動補正し、3Dで骨格を高精度に抽出する。
そして26年度からは『時間・空間的制約の排除(ホームケアサポート)に取り組む。理学療法士のスキルをAIで実現したり、理学療法士のノウハウを遠隔で提供するという。
「ここは予防医療になりますが、体のちょっとした異常や最近歩くのが遅くなった、転んで左足が痛いといった症状と、実際の体の動きを分析することで、整形外科にかかったり手術をしなければいけない段階になる前に、気付くことができるものを目指しています。これは冒頭でお話しした、20年に当時の東京医科歯科大と取り組んでいたことを発展させたテーマです。例えば高齢者は、転んで自分で歩けなくなってしまうと、そこからどんどん症状が悪化してしまうこともあるので、そうなる前の段階で転ばなくて済むためのデータであったり、日々の理学療法士の指導によって防げるようにするものを実現していきたいと考えています」(小関さん)。
◇
※地域医療構想:急性期から回復期、慢性期まで、将来の医療ニーズの予測を踏まえ、関係者の協議によって地域に必要とされる医療提供体制を組む構想のこと。
※地域包括ケアシステム:高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられることを目指した、地域の包括的な支援・サービス提供体制のこと。
写真は NECと東京科学大学の関係者一同
この記事を書いた記者
- 元「日本工業新聞」産業部記者。主な担当は情報通信、ケーブルテレビ。鉄道オタク。長野県上田市出身。
最新の投稿
 情報通信2026.02.05ビット・パーク、施設予約システムとココBOXが連携
情報通信2026.02.05ビット・パーク、施設予約システムとココBOXが連携 情報通信2026.02.05NHKテクノロジーズ、東日本大震災3D記録映像上映
情報通信2026.02.05NHKテクノロジーズ、東日本大震災3D記録映像上映 情報通信2026.02.03アンリツ、透過型NIRによる錠剤全数検査装置
情報通信2026.02.03アンリツ、透過型NIRによる錠剤全数検査装置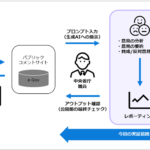 情報通信2026.02.03富士通、生成AIでパブコメ業務効率化
情報通信2026.02.03富士通、生成AIでパブコメ業務効率化


