
【セミナー報告】GNSS脆弱対策って何?
インターネットイニシアティブ(IIJ)主催の技術セミナー「GNSS TimeSync 2025」が、10月22日にIIJグループ本社(東京都千代田区)及びオンラインによるハイブリッドで開催された。共催は精工技研、セイコーソリューションズ、古野電気、丸文、Calnex Solutions plc、IIJエンジニアリング。
同セミナーは、GNSSによる時刻同期をテーマとし、業界の動向やレジリエントな受信システム、今後の展望について一望できる、日本初の「GNSS時刻同期に特化した技術セミナー」として開催した。業界の第一人者が、分野を横断しGNSS時刻同期の現在と将来を解説した。会場ではセミナーの前後に、主催・共催企業によるブース展示も行った。内閣府、情報通信研究機構(NICT)のコーナーも用意した。
近年、GNSS(全球測位衛星システム)はNTP、PTPの普及と相まって、時刻同期のための源信号として幅広く用いられるようになった。理論上地球のどこにいても安定した時刻が得られる一方で、受信システムの構築には電波、アンテナ、同軸ケーブルやノイズ対策といった高周波技術の理解が求められる。特にIT分野の技術者に対し、こうした技術を一括して伝える必要性が増大している。また最近話題となるジャミング・スプーフィングについても「正しく怖れる」ためには正しい情報による理解が必要だ。
今回のセミナーのねらいはNTP、PTPなど時刻同期プロトコルに接する技術者に、その前段となるGNSSにまつわる最新の技術動向を伝えたもの。第一線のメーカーや研究機関の技術者・研究者が講演。放送・通信・金融を含め、時刻同期技術に関心のある人たちが熱心に聴講していた。
「GNSS TimeSync 2025」で、古野電気システム機器事業部開発部主任技師の橋本邦彦氏が「GNSSによる高精度時刻同期とその脆弱性対策」と題して講演した。
GNSSは、誰でもどこでも無料で利用できる高精度な時刻同期手段として、通信・放送・金融・電力など多くの分野で活用されている。しかし、マルチパスや電離層などの環境依存性、GNSSセグメントのエラー、他の無線からの干渉などの脆弱性を内包している。特に近年は、ジャミング・スプーフィングといわれる意図的なRF干渉による攻撃が深刻化している。
講演では、GNSSによる高精度時刻同期の基本的な原理を解説し、GNSSの脆弱性とその対策を整理した。
橋本氏の主な講演内容は次の通り。
はじめに、古野電気の歴史と製品群を紹介します。当社は舶用向け電子機器のメーカーでソナーやレーダー、魚群探知機で有名な会社です。海の中で自分の位置を算出するのは非常に重要で、GPSのナビゲーションシステムというのをGPSが公開されてわりと早い段階、1986年頃から古野電気はGPSのナビゲーションに携わっています。
時刻同期という目線では、民生用で、1998年から時刻同期用のGPS製品を提供しています。
まず基本的なところから時刻同期とは何か、GNSSによる高精度時刻同期の基本的な原理、高精度時刻同期手段の比較についてお話しします。
時刻同期とは、端的に言うと一人ひとりの時計をみんなの時計に合わせることと私は考えています。みんなの時計とは何かというと国際的に協調した時計とは、UTC(協定世界時)時刻というのがあって、みんなの時計もそれに合っているものです。各国の研究機関がそれぞれUTCを保有しており、それぞれの研究機関のUTCが互いに比較して、概念的なUTCを生成します。GPSがどう関連するかというと、UTCをベースにGPSの時刻が生成されて、それがコントロールセグメントを通じて、それぞれのGPSの衛星の時刻を同期させます。衛星から送出される信号をGPSの受信機が受け取って、計算することによってUTCに同期したタイムパルスを生み出すことができる形になっています。
衛星からの信号がGPSのアンテナに入力されますが、ここでのポイントは一方向、GPSの電波が皆さんにブロードキャストされて、レシーバーがそれを受け取ることで測位演算する、このことによってUTCに同期した時刻情報を提供できるところです。そして、産業用として世界トップクラスの同期性能を発揮できて、原理的にUTCにつながっていますので、長期的に安定な時刻を提供することができるのです。
GPS、GNSSの生成する時刻情報は重要なインフラで使われています。テレコミュニケーションとかブロードキャストなどで使われています。特にGNSS受信機はPRTC(プライマリー・リファレンス・タイム・クロック、GNSSから時刻を受信する時刻基準装置)として広く使われています。1PPS(パルス・パー・セカンド、衛星が1秒間に1発だけ出力する非常に正確なパルス波)として知られる高精度時刻信号を提供します。PRTCの頭文字のひとつは『最初の』の意味なので、時刻を生成する第一の手段として使われていることを強調したいと思います。1PPSでUTCに同期した信号を提供することがポイントになると思います。
さきほど触れました1PPSについては、電気的な信号で1秒パルスと同じ意味で、1秒に1回UTCに同期した電気信号を発することができるというのが、このGPS受信機のタイミング用、時刻同期用のGPS受信機の特長になっています。この1PPSの立ち上がりが何年何月何日であることを表す時刻データ(TOD)とリンクすることで、立ち上がりが何時何分何秒かもわかるようになっています。これは、いわゆる時報の出し方と一緒でピ、ピ、ピ、ポンのポンっていうのがパルスになると思ってください。時刻の出し方は時報と同じで、例えば「午前10時ちょうどをお知らせします」ということは、GNSSが2025年10月22日10時00分00秒というデータ出力を行い、データ出力の後に立ち上がるパルスがUTCに同期するということです。
近年は代替手段でLEOの話も出てきていますし、このほかPTP、White Rabbit、BPS、NTP、JJYと呼ばれている技術もあります。
この中でGNSSは、手軽にUTCを取得できる反面、屋内で使用できない、ジャミング/スプーフィングの攻撃(GPSやGNSSの信号を妨害したり、偽装したりするサイバー攻撃のこと)に脆弱であるとされています。GPSを含むGNSSは生来の脆弱性をもっています。このことはGPSが重要インフラでの使用と同時に指摘され続けています。
脆弱性のひとつ目が環境依存によるものです。例えばGPSのアンテナを上げて、アンテナに落雷があったらGPS測位を続けることができないので、そういうのがひとつ。あとはマルチパス。衛星から電波を受信機に送りますので、その過程においてダイレクトに電波を受信しなくて、ビルによって反射する、そういうことによってGPSの性能というのが劣化します。3つ目は電離層の揺らぎによってGPSの測位の結果が変化します。
次にジャミングですが、こちらが近年特に注目を浴びており政情不安などがあって、ジャミング攻撃が多く報告されるようになっています。次にスプーフィングですが、これはGPSを模擬した信号を意図的に出すことによって、測位結果、タイミングをずらすような攻撃が実際に存在します。
このほか、隣接バンド帯のトランスミッターで、GPSの受信機を置くところが強い無線信号、例えばLTEの基地局とかに置かれる時においてはRFによる干渉を受けることになります。最後はGPSセグメントエラー。GPSも人が運用するものなので、GPSそのものがエラーを発生する場合があると言われています。GNSSの利便性(誰でも使える、どこでも使える、いつでも使える、無料、受信機の数に制約がない)であり、それと脆弱性は『コインの裏表』です。
次に脆弱性対策をお話しします。
ひとつは衛星信号断(Holdover、ホールドオーバー)。GNSS脆弱性対策の第一歩は、GNSS信号断への対策です。GNSS DO(GNSSで調律された発振器のこと)は搭載の発振器を用いて、GNSS信号断に自走(Holdover)で時刻精度を維持します。GNSS DOがGPSのレシーバーと発振器を一緒にすることによって、GPSが途絶えたときに、発振器によって、時刻精度を担保する仕組みがHoldoverです。例えばアンテナに落雷があったときに、GPSの受信からホールドオーバーに移行します。
2つ目はマルチパスの対策を紹介します。GPSのマルチパスでは都心部でカーナビゲーションが劣化するなどはご存じと思います。マルチパスは非常に大きな問題で、その中でどういうところにアンテナが設置されるかというとやはり都心部にアンテナが多く設置されると。そこで思った以上に想定された数字を大幅に超えて、劣化する、通信が途絶えることが大きな問題になっています。その対策として、古野電気はNTTと共同で2018年に「『少数精鋭』の衛星選択で世界最高水準のGPS時刻同期精度を実現~シビアな受信環境で精度を飛躍的に向上するマルチパス対策GNSSレシーバを開発」を報道発表しました。DSS(ダイナミック・サテライト・セレクション)により、時刻精度劣化に大きな影響を与える不可視衛星(NLOS)を排除するものです。
次にジャミングですが、紛争地域で常用的になってきており、対策が求められています。ここではGPSの受信機の中にフィルターが入っており、不要な妨害波を除去する受信機が多くなっています。GNSS受信断時の対策と同様、Holdoverも対策となり得ます。ジャミング攻撃の方向を検出してその方向のアンテナゲインを抑える「ヌルステアリングアンテナ」も提案されています。
次にスプーフィング対策としてはメッセージ認証、GNSS Firewallなどの対策専用機器などです。
◇
続いて、「AU―500」の携帯電話基地局干渉低減実験について。
当社、古野電気の「AU―300/AU―500」は、携帯電話の基地局などに使用されることを想定した時刻同期用GNSSアンテナです。「AU―300」はコストパフォーマンスに優れたシングルバンド受信(L1)、「AU―500」は堅牢性を追求したデュアルバンド受信(L1/L5)となっています。
特長は▽高い耐候性①保存/使用温度範囲:マイナス40度C~プラス85度C②防水・防塵:IP67③雷保護:IEC6100―4―5④積雪を防ぐドーム型構造▽高い可用性①広い電圧対応②高い増幅③マルチパスの影響を軽減するグランドプレーン付④携帯電話の基地局からの干渉を低減する対策を施したGNSSアンテナ。この④の部分についてですが、私どもは、干渉低減の対策の効果を実際の現場で確認しました。2つのGNSSアンテナを携帯電話基地局アンテナのそばに設置しました。ひとつはAU―500そのもので、基地局からの干渉を低減するアンテナで、もうひとつはそうではないアンテナで、その結果、AU―500の基地局からの干渉低減効果が有効であることを示しました。
今日のお話しをまとめると次の通りになります。①GNSSは利便性と脆弱性をあわせ持ちます②様々な代替手段が脆弱性に対処するために提案されています③干渉に対抗するために、GNSSと代替手段は協力する必要があります④GNSS受信機は干渉を検出して、PPSが劣化する前に代替手段に切り替えることが好ましいと考えます⑤そのためには、保護的検出能力が必要です。
◇
橋本氏のほか次の4名が講演した。
「社会インフラを変えるPTPと時刻同期の進化」と題して、セイコーソリューションズ戦略ネットワーク本部戦略ネットワーク営業統括部タイミングソリューション営業部長の鈴木康平氏が講演した。
同セッションでは、通信事業者、製造業、金融、そしてAI基盤に至るまで、産業ごとの活用事例を紹介しながら、時刻同期の現状と課題、そして今後の展望について述べた。
「試みてわかる。GNSS受信システム構築の課題とその対策」と題して、精工技研機器事業部の藤浪圭氏が講演した。
同講演では、実現場で生まれる様々な課題に対し、GNSSアンテナから受信機までをいかにスマートに構築するかについて、GNSSの電波をファイバで伝送する手法も踏まえて述べた。
「7機体制を迎える準天頂衛星システムみちびき ―時刻を提供する社会インフラとしての役割」と題して、内閣府宇宙開発戦略推進事務局参事官/準天頂衛星システム戦略室長の三上建治氏が講演した。
「高精度時刻配信の現状と国際動向、NICTの取り組み」と題して、国立研究開発法人情報通信研究機構電磁波研究所電磁波標準研究センター時空標準研究室室長の井戸哲也氏が講演した。
◇
古野電気のブース=写真=で担当者から同社製品について特長を聞いた。
フィールド・タイムシンク・ジェネレーター「TB―1」は、UTCに同期したIPPSと正確な10MHzを出力する手のひらサイズの「原子時計」。無線システムの保守現場や、研究開発の現場に向けて作られたGNSS基準信号発生器。高精度OCXOを搭載した。UTCに同期した1秒パルス(1PPS)と正確な10MHzで、デジタル放送・5G・V2X開発の現場の時刻同期や周波数測定のニーズに応える。
「TB―1は中に基準周波数発生器が入っています。その役割は、GPSのアンテナからケーブルでつないで、TB―1で時刻同期させて、そこから正確な時刻情報を、周波数の情報を出力する筐体です。簡単にコネクター接続するだけで、お客様が正確な時刻情報を取り出せるといったことが特長になります」(古野電気)。
時刻同期用GNSS受信モジュール「GT―100」は、L1/L5の2周波GNSS受信モジュール。2周波受信により世界最高水準の堅牢性と時刻精度を実現。全世界のGNSSに対応した新世代の受信モジュール。時刻精度は世界最高クラスの4・5ns未満。耐マルチパス技術「ダイナミック・サテライト・セレクション」を搭載し、都市部や窓際にアンテナを設置した場合でも時刻精度の劣化を最小限に抑える。
「GT―100は2周波受信ができる受信機になります。L1帯とL5帯の両方を取れる受信機になります。もう一つのポイントはジャミング対策。妨害波への対応がこの2周波受信の良いところで、例えばL1帯って言われるような一般的によく使われる周波数帯で、そういった妨害が発生した時に、もう一つの周波数帯であるL5帯で受信を継続できるのです。ジャミングが起きても正確な時刻情報を出力し続けるような堅牢性を持ち合わせたモジュールになります」(古野電気)。
この記事を書いた記者
- 元「日本工業新聞」産業部記者。主な担当は情報通信、ケーブルテレビ。鉄道オタク。長野県上田市出身。
最新の投稿
 情報通信2026.02.05ビット・パーク、施設予約システムとココBOXが連携
情報通信2026.02.05ビット・パーク、施設予約システムとココBOXが連携 情報通信2026.02.05NHKテクノロジーズ、東日本大震災3D記録映像上映
情報通信2026.02.05NHKテクノロジーズ、東日本大震災3D記録映像上映 情報通信2026.02.03アンリツ、透過型NIRによる錠剤全数検査装置
情報通信2026.02.03アンリツ、透過型NIRによる錠剤全数検査装置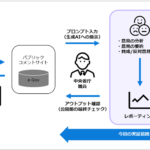 情報通信2026.02.03富士通、生成AIでパブコメ業務効率化
情報通信2026.02.03富士通、生成AIでパブコメ業務効率化


