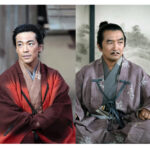TOKYO FM開局55周年 特別インタビュー 技術局長・川島修氏に聞く“音声マンとして矜持”
■半世紀以上にわたり「最上の音」をリスナーに提供
――今回は、開局55周年ということで、放送・制作技術の面から御局の歩みに迫るとともに、オーディオコンテンツ制作の肝についてお聞きしたいです。まず、55年の歴史の中で、川島さんが特に印象的とお考えになる技術をあげていただけますか
数多くありますので、いくつかに絞ってお話しします。まず、1985年に行われた、衛星回線を使った海外からのデジタルステレオ生中継。これは当時、まだどこのラジオ局もやっていなかったはずで、かなり早い取り組みだったと思います。私自身が関わったことでは、1994年の『見えるラジオ』をあげたいです。これは、FM放送信号の隙間を利用して送った文字情報を専用デバイスで受信し、テキストをポータブル受信機やLEDに表示させるというもので、当時はかなり注目されました。その後、この技術を応用した『パパラビジョン』という大・中型の電光掲示板が開発され、震災被災地の避難所に設置し、地域住民の皆さんにライフライン情報等を提供しました。インターネットを使った技術では、2010年にiPhoneでラジオ放送が聴けるIPサイマルサービスを開始しました。これはradikoのスタートとほぼ同時期で、ラジオと通信が融合したサービスの先駆けとなりました。

「見えるラジオ」(写真提供:TOKYO FM)
送信関連では、2013年に東京タワー最頂上部の新アンテナからの送信がスタートしました。これにより、サービスエリア内での受信環境が飛躍的に改善し、リスナーの方々にクリーンかつ快適な音で我々の放送を楽しんでいただくことが可能となりました。さらに、ISDN回線でステレオ音声を伝送する技術は、当社がいち早くNTTや各メーカーと一緒に取り組んだもので、ラジオ業界では広く利用されてきました。このようにあまり知られていないけれど、画期的なことを多く手掛けてきたと思います。
――御局は果敢に新しい技術にチャレンジしている印象があります
たしかに当社は他社に先んじて初めてのことに取り組むことが多いかもしれません。それは、元々1960年の実験局から始まっているので、そういう企業風土というか、伝統的なDNAのようなものがあるのかもしれません。
アナログ時代の過酷な試練!
――川島さんが1990年に入社された時はミキサーとして入社されたのでしょうか
当社では入社後、技術局に配属された新人はまず、スタジオでのミキシングから運行、送出・送信など、放送技術に関わる全ての業務を経験します。テレビ局と違い、人数の少ないラジオ局の技術者は一通り何でもこなせなくてはいけませんから。その後、ミキシングが得意な人、送出・送信が得意な人、運行技術に向いている人など、その各人の適性に合わせて担当業務を任されることになります。私は音楽が好きだったことや、ミキシングの作業が好きだったということもありましたので、ミキサーとしてスタジオ制作を担当することになりました。
――入社された頃のスタジオ機材はもちろんアナログですよね
全てアナログです。音声卓もそうですし、テープレコーダーはオープンリール、アナログレコード用のターンテーブルもありました。エフェクターはデジタルの機材が出始めた頃ですが、まだまだアナログ機器が支配的でした。
――その頃のエピソードがあればお聞きしたいです
そうですね…。当時、とても厳しいプロデューサーの方がいらっしゃって、新人研修のある日、その方がアナログレコードを持って我々新人たちの前に現われました。何をするのかと思っていたら、突然カッターでそのレコードにがーっと傷を付けたんですよ。そして、そのレコードをプレーヤーにかけて、オープンリールテープに録音されたのです。盤面に傷が付いているから、もちろん激しく音飛びします。それでその録音したテープを切り貼りして、ちゃんと聴けるように直せ、という課題を与えられました。一晩中かけて何とか直しましたが、その時は〝すげえところに入っちゃったな〟と思いました(笑)。
(以後、全文は7月25日付けの紙面に掲載)
この記事を書いた記者
- テレビ・ラジオ番組の紹介、会見記事、オーディオ製品、アマチュア無線などを担当