
イートラスト、クラウド型防災監視カメラ「eT002」発売
夜間撮影の性能が格段に向上
イートラスト(東京都台東区、酒井龍市代表取締役社長)は、クラウド型防災監視カメラの最新モデル「eT002」を4月に発売した。同社は、全国の自治体を中心に河川監視カメラ約2500台をはじめとした防災監視システムを導入している。その経験と知見を活かし「eT002」は、より高性能かつ現場の生の声を活かしたカメラシステムへと進化させた。特長は設置環境にあわせた柔軟なシステム構築、夜間画質の向上と自由な直角調整、豊富な実績に基づく高い信頼性。酒井龍市代表取締役社長、ソリューション開発事業本部開発部開発課課長の臼井秀行さん、ソリューション開発事業本部営業部営業課(営業グループ)担当課長の中川浩之さん、ソリューション開発事業本部営業部営業課(営業グループ)波多野仁美さんの4名に話を聞いた。
――最近の防災監視システムの市場環境についてお気づきの点をお聞かせください
酒井 「河川監視に関して、普及は一段落ついている感じもしますが、絶対数としてはまだまだ足りていません。河川以外にも道路やため池などいろいろなところで、防災ソリューションはこれからニーズがどんどん増えてくると思います。ただ、景気動向や予算の仕組みという点でなかなか加速していかないという、ジレンマ的な部分も感じています。メーカー側をみると、AIというキーワードも含めて新規参入するところが増え始めています。それから、メインで活動している大手メーカーから中小、ベンチャー企業と入り乱れて、再編が進む最中なのではと感じてます」
――続いて開発を担当された方からクラウド型防災監視カメラ「eT002」の開発のポイントをお話しください
臼井 「まずひとつ前のモデル『eT001s』のお話しをします。こちらは国土交通省主導のプロジェクトで、簡易型河川監視カメラのカテゴリーにおいて従来の高価なカメラシステムよりもひとつ下の価格帯の製品を普及させて多くの場所に簡易河川監視システムを導入させるという背景のもとに開発が始まったものです。当社は公募の段階から開発参加している歴史があります。『eT001s』からの基本的なスペックは、ソーラーパネルで電源を供給する、通信はLTEで行い一切配線をすることなく稼働する点です。河川の上流など電線が来ていない場所でもソーラーで電源は供給できますし、LTEの電波が届けば監視ができるのでたいへんご好評いただいています。同業他社と比べてソーラーやバッテリーも小型になっています。『eT001s』は電源が落ちたことはほとんどありません。そういった開発コンセプトを新モデルは継承しています。お客様にご安心いただいて使っていただけているという高信頼性を踏襲しつつ『eT002』を自信をもって市場に投入しました」
――リニューアルした点でいちばんアピールしたいところはどこでしょうか
臼井 「夜間画質の向上です。夜間撮影の性能は格段に上がっています。従来機の最低被写体照度0・02ルクスから新モデルは0・005ルクスに向上しました。夜間撮影でも昼間に近い明るさの画像を取得できます。夜の写りということでは従来機でも相当頑張っていましたがさらに越えなければいけないとの思いでカメラモジュールをいろいろなパートナー企業のパーツを検討しながら川の監視で問題がないように仕上げました。無線や水位計、レーダーといった分野では熟練した技術者がいましたが、カメラモジュールに関しては我々もある程度は経験があったものの奥がとても深くて、〝あちらを立てればこちらが立たず〟のような世界でした。さらにポイントは保守メンテナンス作業が遠隔で行える点です。万が一にも不具合が生じた場合、デバイス状態やリソースの監視、リブート作業を遠隔でサポートします。お客様へのご迷惑を最小限にするとの思いで遠隔の保守機能をかなり盛り込んだ内容になっています。このほか新機能では広角と望遠との画角調整が自由なバリフォーカスレンズを採用しました」
酒井 「『eT001s』はクラウドをベースにした簡易型河川監視カメラというスタートでした。その普及が一段落してこれからさらに増設や更新の需要が始まる中で、基本性能をより向上させたのが『eT002』で、低消費電力、省電力システムにより無日照状態でも7日間稼働、クラウドによる機能などを踏襲しながら、さまざまな新機能を加えてバージョンアップしました。1年間実証実験を実施し、新モデルの受注をすでにいただいてまもなく納品が始まります。新潟県や群馬県のある自治体に1号機が納入されます」
――〝お客様へのご迷惑を最小限にするとの思い〟は大事なことですね
酒井 「クラウド型のカメラ水位計の製造販売をスタートしてから7年ほど経ちました。当社は通信工事の会社でカメラ水位計は新規事業で取り組みを始めました。今回、世代が変わるにあたって、品質管理面で今まで以上に体制を固めました。遠隔メンテナンスもそのひとつです。今まで以上により高度な品質管理を新モデルからどんどん構築して進めていきます。今までも遠隔でカメラの設定などはできていましたが、そのできる領域をぐっと深めました。ファームウェアもある程度のバージョンアップは遠隔でできていましたが、万が一の時に、現場に行かなければいけない、機械を取り外して持って来なければいけないといったことはあってはならない。それが〝お客様へのご迷惑を最小限にするとの思い〟です」
写真は 「eT002」の設置現場のようす
全文は6月1日付4面に掲載
この記事を書いた記者
- 元「日本工業新聞」産業部記者。主な担当は情報通信、ケーブルテレビ。鉄道オタク。長野県上田市出身。
最新の投稿
 情報通信2026.02.05ビット・パーク、施設予約システムとココBOXが連携
情報通信2026.02.05ビット・パーク、施設予約システムとココBOXが連携 情報通信2026.02.05NHKテクノロジーズ、東日本大震災3D記録映像上映
情報通信2026.02.05NHKテクノロジーズ、東日本大震災3D記録映像上映 情報通信2026.02.03アンリツ、透過型NIRによる錠剤全数検査装置
情報通信2026.02.03アンリツ、透過型NIRによる錠剤全数検査装置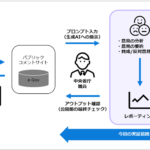 情報通信2026.02.03富士通、生成AIでパブコメ業務効率化
情報通信2026.02.03富士通、生成AIでパブコメ業務効率化


