
アンリツの「におい検査機」 人に代わって自動でにおいをかぎ分ける
アンリツ(濱田宏一社長)は、人が直接においをかぐ官能検査を自動化する「におい検査機」を一般向けに販売すると発表した。人が感じることのできる五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)の中で、これまで自動化が難しいとされてきた嗅覚だが、新たに開発されたにおいセンサとAI学習機能により、あらゆるにおいを数値化し可視化する。
製品の開発や生産現場では、現在においても官能検査が一般的だ。加えて、これまでにおい分析に使われてきた「ガスクロマトグラフィー」は臭気の成分を特定できる一方、微妙なにおいをかぎ分けるには限界があるとされてきた。アンリツの検査機は成分を分析するものではないが、においの違いを簡便に可視化できる利点がある。これにより、生産工程の検査員の負荷軽減、人員不足の解消、品質の安定化に貢献する。
人の嗅覚は、400種類の嗅覚受容体がにおいに含まれる化学物質のパターンを認識することで、においの特徴を記憶するとされている。
一方、検査機には人の嗅覚受容体に相当するにおい吸着膜が40種類あり、それぞれの膜ににおい分子が付着すると、各センサの周波数(センサとして使われている水晶振動子の周波数)が変化する。その40種類の変化を捉えることで、においの識別が可能となる。さらに、AIを駆使して高次元データを変換し、評価軸に表すことでにおいを可視化する。
検査機には6本のガラス瓶が装着されており、最大で6サンプルの検査ができる。1サンプルは1回3分で測定が可能だ。また、AIによる学習機能を使い多数のデータを集める場合は、付属のソフトウエアで測定回数を設定することにより、効率的な自動測定が可能になる。測定結果は、即時に解析用のアプリにアップロードされ、AIによる解析で分別や類似度の判定を行うことができる。
対象市場は研究開発では飲料や酒類のにおいによる分類、食品製造ではスパイスなど香りの管理、日本酒の発酵度合い、品質管理では出荷後に寄せられた製品の異臭についての調査補助。
コーヒーやお茶の研究開発、日本酒やワインの出来栄え評価など、幅広い用途で使用することを想定している。。研究開発においては、自社製品のにおいの特徴を他社と比較することも可能だ。そのほか、製造されたゴマ油が出荷基準を満たしているか香りで確かめることで検査員の補助ができ、小麦粉のカビ臭を覚知することで品質管理にも貢献する。
「電波タイムズ」の取材に対してアンリツのコーポレートブランディング部は「このAI学習機能は、〝教師あり〟の機械学習を採用しています。ディープラーニングとは異なる手法です。判定したい複数のにおいを学習させています。あらゆるにおいを学習したデータベースはありません」と答えている。
※におい可視化のしくみ:においの検出は人の鼻と似たしくみだ。においに含まれる化学物質(におい分子)が、人の嗅覚受容体に相当するセンサの感応膜に吸着すると、センサの特性(共振周波数)に変化が起こる。各々のセンサの信号を統計的手法で解析することで、においを分別・特定することが可能。AIを活用してあらかじめにおいを学習することで、「被検査品のにおい」にどの程度の確率で類似しているかを判定することができる。
この記事を書いた記者
- 元「日本工業新聞」産業部記者。主な担当は情報通信、ケーブルテレビ。鉄道オタク。長野県上田市出身。
最新の投稿
 情報通信2026.02.05ビット・パーク、施設予約システムとココBOXが連携
情報通信2026.02.05ビット・パーク、施設予約システムとココBOXが連携 情報通信2026.02.05NHKテクノロジーズ、東日本大震災3D記録映像上映
情報通信2026.02.05NHKテクノロジーズ、東日本大震災3D記録映像上映 情報通信2026.02.03アンリツ、透過型NIRによる錠剤全数検査装置
情報通信2026.02.03アンリツ、透過型NIRによる錠剤全数検査装置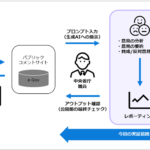 情報通信2026.02.03富士通、生成AIでパブコメ業務効率化
情報通信2026.02.03富士通、生成AIでパブコメ業務効率化


