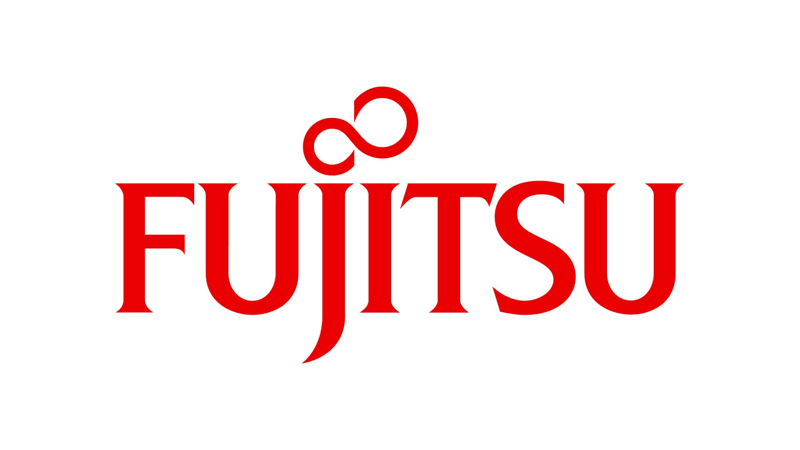
富士通、藻場のブルーカーボンを効率よく定量化
富士通は、海洋の状態をデジタル空間上へ再現し、海洋を構成する環境の変化などを予測する海洋デジタルツインの研究開発の一環として、海藻・海草に取り込まれ貯留される炭素であるブルーカーボンの定量評価を迅速・高精度に行い、藻場の回復・保全などを支援する技術を開発したと発表した。
本技術は、海流の中でも従来の100倍の速さで自動的に海中データを収集する水中ドローン自動航行技術をもとに、海洋生態学とAIの融合により海中に群生している海藻・海草の種類、被度を85%以上の高精度で認識する藻場認識・モデル化技術と、藻場に対する回復・保全施策の事前検証を支援する藻場創出シミュレーション技術の3つの要素技術で構成される。これらの技術を活用して、ブルーカーボンクレジットの認証取得を支援するエンドツーエンドシステムも構築した。
本システムを活用して、一般社団法人宇和海環境生物研究所、愛媛県漁業協同組合吉田支所、宇和島市とともに宇和海でのブルーカーボンの定量化を実践し、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合にブルーカーボンクレジット の認証・発行を申請した結果、認定率95%というトップクラス評価のJブルークレジット認証を獲得し、技術の有効性を確認した。
本システムをはじめとする海洋デジタルツインの取り組みを、2025年11月27日(木曜日)から11月29日(土曜日)まで神戸国際展示場で開催される展示会「Techno-Ocean 2025」に出展します。今後、本システムを活用し、藻場 など環境保全に向けた計測、施策の立案を支援し、脱炭素や生物多様性保全などの社会課題を海から解決することを目指す。
この記事を書いた記者
- 元「日本工業新聞」産業部記者。主な担当は情報通信、ケーブルテレビ。鉄道オタク。長野県上田市出身。
最新の投稿
 CATV2026.01.10イッツコム、防災活動の功績で青葉消防署から感謝状
CATV2026.01.10イッツコム、防災活動の功績で青葉消防署から感謝状 CATV2026.01.09イッツコム、アートラッピング電車特番
CATV2026.01.09イッツコム、アートラッピング電車特番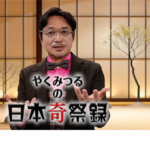 CATV2026.01.08日本デジタル配信、新番組「やくみつるの日本奇祭録」
CATV2026.01.08日本デジタル配信、新番組「やくみつるの日本奇祭録」 CATV2026.01.08イッツコム「おうち防災スタートセット」
CATV2026.01.08イッツコム「おうち防災スタートセット」


